
子どもに「やってはいけない𠮟り方」とは?“絶対に”言うべきではない言葉ワースト3
子育ての中で、つい感情的に怒ってしまった経験はありませんか?
「きちんと伝えたい」「良くなってほしい」と願って発した言葉なのに、あとから後悔してしまう……。そんな時には、“しかり方”を見直してみましょう。
叱ることは、愛情の表現のひとつ。でもその「言い方」ひとつで、子どもの心に与える影響は大きく変わります。
精神科専門医で精神保健指定医、子どものこころ専門医である大和 行男先生監修のもと、「NGな𠮟り方」をお伝えします。
「叱る」は伝え方しだいで、子どもの心を支えるものになるが……
子どもを正しい方向へ導きたいという思いがあっても、言い方によってはその思いが伝わらず、かえって心に傷を残すことがあります。
とくに注意したいのが、脅すような言い方や他人との比較、そして存在を否定するような言葉です。
1.脅すように叱る
「○○しないと怖い人が来るよ」と脅すように叱ってしまうと、子どもは恐怖だけが記憶に残り、行動の理由を理解しにくくなります。
2.比較して𠮟る
「○○ちゃんはできたのに」と他の子と比べる言葉も、子どもの自己肯定感を下げてしまう可能性があります。大切なのは、“本人の成長”に目を向けることです。
3.否定の言葉で𠮟る
そして、「いなくなればいいのに」「何をやってもダメ」といった否定の言葉は、子どもの心を深く傷つけます。
一時の感情であっても、その一言が子どもに長く影響を与えることがあります。
愛情が伝わるしかり方に変えていくために。言い回しを変えるコツ
叱ることそのものが悪いわけではありません。ただ、その伝え方を少し変えるだけで、子どもにとっては受け入れやすく、安心感のある声かけになります。
たとえば、「○○しなさい」ではなく「○○してくれると助かるな」と伝えたり、「なんでできないの?」ではなく「ここまではできたね」と前向きな言葉に言い換えるだけで、雰囲気が柔らかくなります。
「○○しなさい」→「○○してくれると助かるな」
「なんでできないの?」→「ここまではできたね」
叱ったあとに後悔することが多いと感じるなら、一度、日々の言葉を振り返ってみてください。たったひと言の工夫で、子どもとの関係が少しずつ変わっていくはずです。
監修者プロフィール
こころと美容のクリニック東京
大和 行男 先生
東京大学教育学部を卒業後、会社員を経て新潟大学医学部入学。同医学部卒業後、東芝病院、東京大学医学部附属病院での初期研修を終え、東北地方と首都圏の精神科病院で研鑽を積み、精神科専門医、精神保健指定医、子どものこころ専門医を取得。
<Edit:編集部>
※本記事は、子育てライフで掲載されていた記事を、MELOS編集部が内容を精査・加筆のうえ再構成したものです。


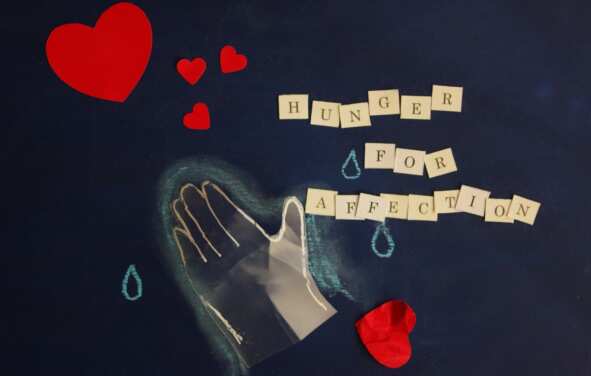
 「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは
「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは