
高校野球は“日本社会の縮図”。山崎エマ監督といだてん演出・井上剛が語り合った、甲子園を描くドキュメンタリー映画
日本の「高校野球」をテーマにしたドキュメンタリーが、昨年(2019年)、アメリカ全土で大きな話題となったことをご存知でしょうか。その作品とは、夏の甲子園100回大会(2018年開催)に挑む横浜隼人高校、および花巻東高校を1年間にわたり長期取材したドキュメンタリー映画『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』です。
国内でも8月21日より順次公開となりました。一体、どんな内容なのでしょう? 都内で9月17日に実施された、関係者によるトークショーの模様と絡めながら、本稿で紹介していきましょう。
全米で放送された「甲子園」を描くドキュメンタリー
『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』で監督を務めたのは、ニューヨークを拠点に活躍する女性映像作家の山崎エマさん。2019年のNHK大河ドラマ『いだてん』の紀行コーナーを担当した縁もあり、今回のトークショーには、『いだてん』でチーフ演出を務めた井上剛さんも招かれました。

▲監督を務めた山崎エマさん(左)と、『いだてん』のチーフ演出 井上剛さん(右)
本作は「高校野球という日本独自の文化を海外に紹介したい」という監督と制作陣の熱い想いから、日米の国際共同制作で誕生したもの。すでにNHKではドキュメンタリー作品「ノーナレ 遥かなる甲子園」(2018年)および「HOME 我が愛しの甲子園」(2019年)として映像の一部が放映されていますが、本映画はさらに内容を掘り下げた、94分間の長編作品に仕上がっています。
物語の主役となるのは、夏の甲子園に向けて挑戦する激戦区・神奈川県の横浜隼人高校と、大谷翔平や菊池雄星を輩出した岩手県の花巻東高校の球児たち。横浜隼人高校を率いる水谷哲也監督はキャリア30年のベテランですが、実はその愛弟子が、花巻東高校を率いる佐々木洋監督という親密な間柄です。この2人が織りなすドラマも、映画の見どころのひとつと言えるでしょう。
そして、いまやメジャーリーグを代表する選手へと成長した大谷翔平投手、菊池雄星投手ですが、本編では両選手にインタビューした模様も随所に挟み込まれている構成です。彼らの原点を知りたい米国のベースボールファンの話題を集めたことは、想像に難くありません。
本映画は、アメリカ最高峰のドキュメンタリー映画祭「DOC NYC」(2019年11月)のワールドプレミア上映で評判を呼んだことから、アメリカ最大級のスポーツ専門チャンネル「ESPN」で全米放送されました(2020年6月)。「ニューヨーク・ドキュメンタリー映画祭 2019」では、入選作品にも輝いています。
高校野球は“日本社会の縮図”
それではストーリーの序盤の流れを追いながら、トークショーのやりとりも紹介していきましょう。
映画ではその冒頭、白黒の映像も交えながら、野球が”学生の教育”の観点で広まった背景を説明していきます。『いだてん』でも描かれた通り、日本では明治期において、心身を鍛える名目で近代スポーツ(野球を含む)が一般化されていったのです。やがて国内の経済が急成長する1970年代に入ると、高校野球の世界では徳島県立池田高等学校が一時代を築きました。率いていたのは、厳格な指導で有名だった名将・蔦文也監督。実は横浜隼人の水谷監督は蔦監督の指導を参考にしており、「人間形成」を目指して球児を鍛えるという彼の信念も、映像の中で明らかにされていきます。
純粋に、10代の高校生たちが繰り広げる青春ドキュメンタリーとしても秀逸な出だしながら、同時に「高校野球は“日本社会の縮図”であり、チームのために自己犠牲が尊ばれる球児の姿はサラリーマンの姿に重なる」といったテーマも匂わせる、そんな序盤の展開でした。
以下、トークショーのやりとりから――。
井上:今回、撮影クルーもアメリカの人だったんでしょう?
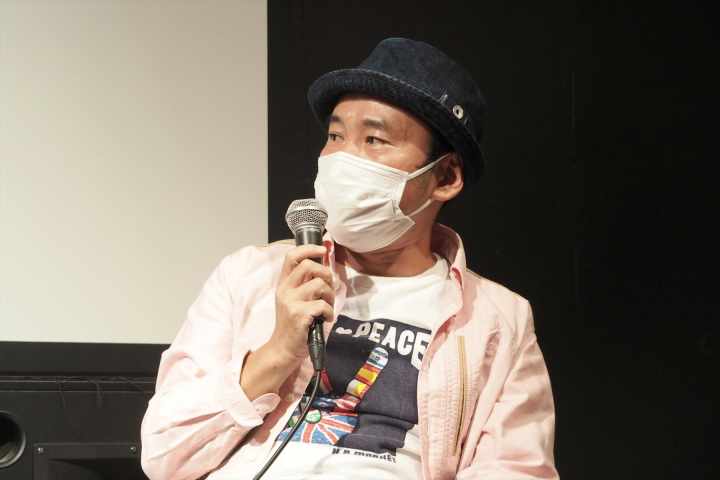
▲井上剛さん
山崎:そうなんです。撮影クルーは、アメリカの大学の同級生でした。撮影監督のマイケルさんの視点を大切にしながら撮ってくれました。日本に初めて来て、日本語も分からない状態で、撮影期間は半年近くにも渡りましたが、頑張ってくれた。外国人が初めて日本に来ると、いろんなことが目に付きますよね。『見て、この靴の並び』とか『電車が時間通りに来ているじゃない』とか。そうした驚きも、丁寧に映像に盛り込んでくれました。彼もアメリカで野球をやっていたそうなんですが『こんなにも違うのか』と驚いたようです。練習方法ひとつとっても、まるで違ったみたい。

▲山崎エマさん
山崎:スポーツのなかった日本に野球の文化が入ってきたとき、日本人はそれを武道になぞらえて『野球道』と捉えて指導しました。『いだてん』でも描かれましたが、それって大昔の話ではないんですよね。ほんの数十年前。ストックホルムオリンピックだって、わずか100年前のことですし。
井上:10代の高校生が感情を抑えて、自分に言い聞かせながら、チームのため人のために尽くしていました。それがグッとくるわけですが、そうは言いながらも、たまに軍隊のように見えて『本当に大丈夫か?』とも思ってしまう。それを外国人のクルーが的確に撮影しているのにも驚きました。
山崎:『いだてん』のときも感じたんですが、日本には自己犠牲の文化がありますよね。誰かが犠牲にならなくちゃ、という。マラソンの金栗四三も、初めてオリンピックに臨んだときは『負けたら切腹』という鬼気迫った雰囲気があった。日本は、そういう傾向が強いんだと思います。ベースボールと野球の違いって、スポーツに犠牲の文化が入っているか否か、だとも思う。それはチームレベルでも、個人レベルでも。
新幹線の横で球拾いする姿
作品では、レギュラー獲得を目指す選手の心の葛藤や、仲間のことを気遣って励まし合う姿などに密着し続けます。監督に叱られ、球拾いする場面にも遠慮なく同行する撮影クルー。山崎さんは「アメリカ人のクルーがいたから、私も『なんで坊主なんですか』とか『なんで監督は怒っていたんですか』など、日本人同士だとあえて聞かないようなことを聞けた部分もあります」と撮影当時を振り返ります。
井上:横浜隼人高校って、真横を新幹線が通る環境なんですね。
山崎:そうなんですよ。外国人が日本ならではの風景を10コ挙げるとしたら、その中に必ず新幹線が入ると思うんです。1964年の東京オリンピック開幕に間に合わせた、日本の技術を代表する公共交通です。その新幹線が走り抜ける真横で、バケツを持って球拾いをする球児の姿があった。いろんなものを象徴するシーンとして使えるかな、と思いました。
井上:規則正しさ、規律の正しさ、組織のためチームのために尽くす姿、そういう日本を見せなきゃと思ったでしょう。それを、あまりナレーションもない中で、映像だけで見せていく。それがとても印象的でした。
山崎:あらゆる場所でマイケルさんが1,000カットくらい撮っていて、その中の20数個くらいを映画に使いました。彼はいつも『撮影監督は、材料は集めるけれど料理が分からないから』と言っていました。だから、あらゆるカットを撮っておいて、料理がどうなっても素材があるようにしておく。そのためには時間をかけて、偶然も味方につけて、というところがあったと思います。
本作品のテーマは高校野球なんですが、それに留まらずに部活動、スポーツ、ひいては日本の教育、日本の社会にテーマが広がっていきます。日本には昔からこういう現場があったから、今、こういう社会になっている。そこには良い部分も悪い部分もあり、いろいろな意見があります。佐々木監督も、これから変わるべきところもある、でも守るべきところもあると仰っていました。変わりどころを間違えたら、日本の良さがなくなる怖さもあると思います。
日本人とアメリカ人の師弟観
外国から日本を見つめ直したからこそ、見えてきた部分がある、と山崎さん。そのひとつが日本人のメンタリティに関するもので「戦後から急成長した日本は裕福で幸せになったはずなのに、メンタリティは戦後のままでした」と分析します。その流れから、日本人とアメリカ人の師弟関係の違いについても言及していきました。
山崎:日本にいたとき、私は日本の良いところに気が付かないでいました。お父さんがイギリス人なんですが、日本にいたときは居心地も悪い気がしていて、19歳でアメリカに渡ったんです。
井上:そうなんだ。高校球児が監督の言いつけを守る姿って、すごいと思うし、ボクが10代だったらできなかったと思うんだけど、エマは19歳まで日本にいて、そうした光景は日常的に見ていた?
山崎:小学校からインターナショナルスクールにいたので、ほかの学校が部活動をやっている姿を見て、すごいというか、どうしてそれをやっているんだろうと思っていました。ひとつのことに専念する、それは野球であっても他のことであっても、自分ができなかったので憧れがありました。スポーツだけでなく、例えば吹奏楽とかもそう。自分を捧げることで達成できることもあるんだ、そんなことを思いながら、外から見ていた感じですね。

井上:ところで水谷監督と佐々木監督は、ふたりとも個性が違いすぎて。本当に師弟関係なんですよね?(笑)
山崎:はい。今となっては弟子(佐々木監督)が恩師(水谷監督)を超える実績を得たのかも知れませんが。私も、ふたりが会えば親友のような雰囲気になるのでは、と思っていたんです。でも全然そんなことはなくて、常に緊張感がありました。私が間にいなかったら、一言も話さないんじゃないかというくらい。お互い独特な空気があり、またこれまでいろんなことを経験し過ぎてきた。ときにお互いのことを思いやり過ぎて、今じゃ言葉にならないところがある、そんな雰囲気でした。これも日本的なことだと思うんです。
アメリカだと、いくら若い頃にお世話になった間柄でも、成功したら恩師をそこまで大切にしないというか、『もう過去のことは良いでしょ』となる傾向があるように思います。塩梅もあるとは思いますが。先輩と後輩の関係も大切ですが、でも行き過ぎると体育会系のダメなところにつながってしまう。
文化を継承していく
映画の終盤では、いよいよ開幕する甲子園に向けた選手選考の模様に密着します。カメラは、レギュラーに選ばれなかった選手たちの落胆する(それでも前を向こうと努力する)姿も映していきます。最後の試合、そして訪れる部活引退の日。BGMやナレーションが極力省かれ、過剰な演出が避けられた映像だからこそ、球児たちの感情の機微がスクリーンからダイレクトに伝わってきます。トークショーでは、世代交代、文化の継承についても話が及びました。
山崎:『いだてん』は、すでに始まっていたオリンピックという世界に、日本のスポーツ界が飛び込んでいく話でした。だからこそユニークなエピソードがたくさんあった。今回はアメリカ人が知らない『甲子園』の文化がテーマだったので、「なんだこの世界は」というユニークな部分を大切に描いていきました。
戦争を経験した人たちが、戦後に高校野球の指導者となりましたが、その指導を受けた(または影響を受けた)人たちが、現在も現場に多く残っています。水谷監督の世代ですね。その次の世代にあたるのが佐々木監督たち。野球に限らずですが、文化って今あるものをベースに変わっていくしかないんです。
日本とアメリカ、どちらの指導が良いということではなくて、アメリカにも良いところと悪いところが絶対にある。そして最前線の指導者は、これまでの文化のつながりを受けながら、試行錯誤を繰り返しながら、より良い指導を目指して変化いくわけです。
井上:(全編を見終えて)私は随所でウルっときました。笑えて泣けた。感動するポイントがたくさんありましたね。はじめはチームと会社をなぞらえていくんだけど、でも途中から、そんなテーマはどうでもよくなって、最終的にボクらを別の場所につれていってくれた。最初の入り口と違うところに出た。ドラマ作品では描けない、素敵な繋ぎだったと思います。とても気持ちが良かった。
《作品情報》
映画『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』ニューヨークを拠点に活躍する映像作家・山崎エマが監督を務め、米・撮影クルーとともに「夏の甲子園」第100回記念大会へ挑む激戦区神奈川県の雄・横浜隼人高校と、大谷翔平や菊池雄星を輩出した岩手県・花巻東高校の球児とその指導者へ1年間に渡る⻑期取材を敢行したドキュメンタリー映画『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』。物語は、30年近いキャリアの中でも特別な想いで記念すべき年に挑む横浜隼人高校の水谷哲也監督、そして水谷の愛弟子である花巻東高校の佐々木洋監督。第100回の夏へ挑むふたりの監督を追いながら、純粋に青春の全てをぶつける高校球児と、教育の最前線にたつ指導者の葛藤、喜びを見つめていく—。
▶公式サイト https://koshien-movie.com/
<Text & Photo:近藤謙太郎>

