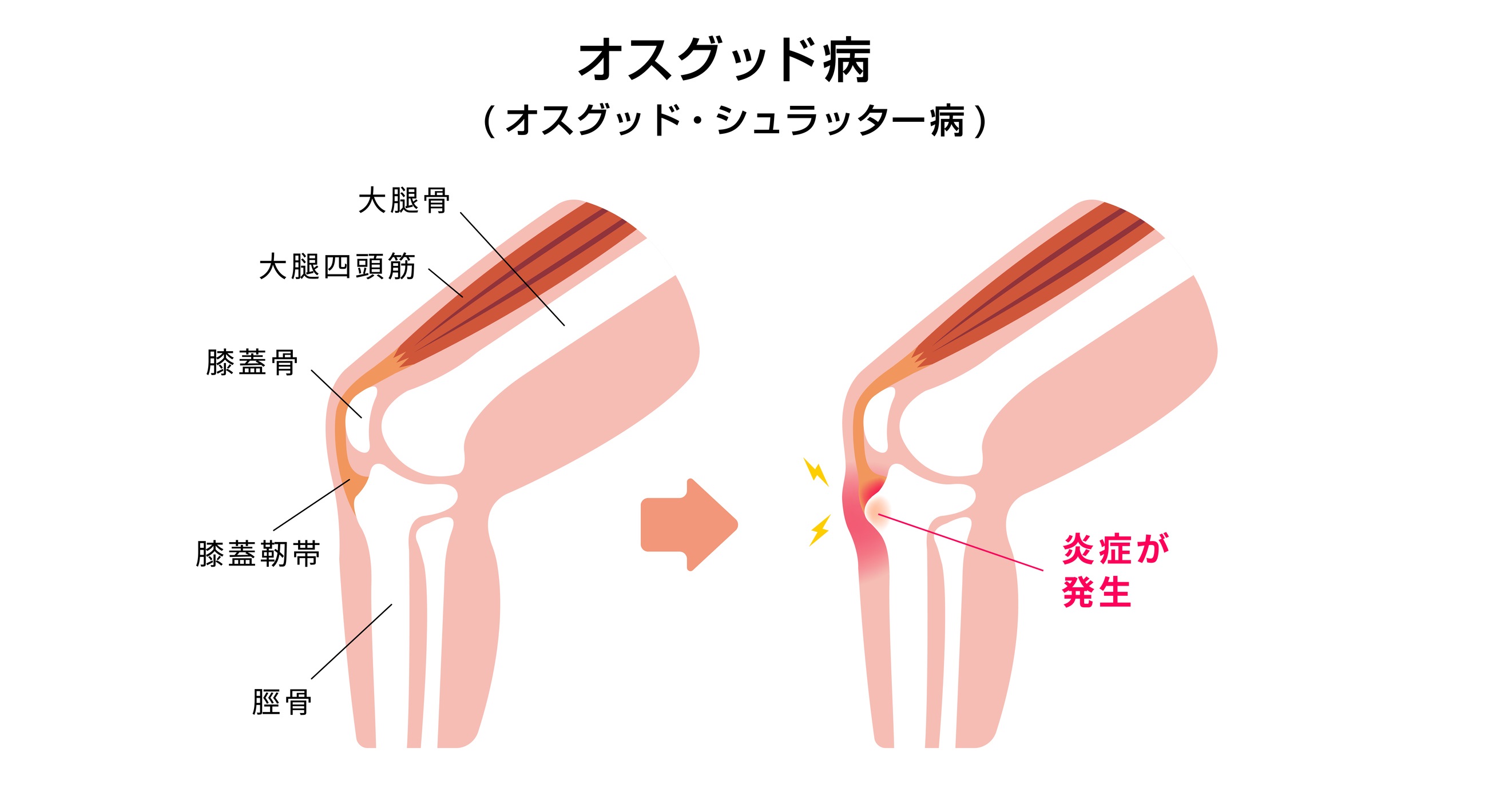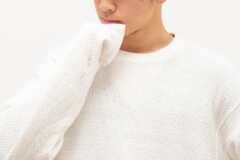過保護すぎ!過干渉な母親に育てられた人は、大人になってどんな影響が出やすい? (2/4)
なぜ父親より「母親」が過干渉になりやすいのか?
父親よりも母親のほうが「過干渉」と指摘されやすいのには、いくつかの背景があります。
まず、日本を含む多くの家庭では、子どもと一緒に過ごす時間が母親のほうが長い傾向があります。毎日の生活習慣や勉強、友達関係など細かい場面に関わる機会が多いため、自然と口を出す回数も増えてしまうのです。

さらに、母親は「子どもを守りたい」「失敗させたくない」という保護本能が強く働きやすいとも言われています。その気持ちは愛情の裏返しですが、度が過ぎると子どもの選択や行動に介入しすぎてしまい、過干渉につながります。
文化的な要因も無視できません。日本の家庭文化では「母親=子育ての中心」というイメージがいまだ強く、しっかり育てなければというプレッシャーが母親に集中します。その結果、子どもの行動を細かく管理しがちになりまです。
ほか、過干渉になりやすい母親にはいくつか傾向がみられます。
- 心配性で「失敗させたくない」と強く思う母親
- 「自分の考えが正しい」と思い込みやすい母親
- 自分自身が不安定で、子どもに依存してしまう母親
- 世間体を気にしすぎる母親
父親からの過干渉もある
母親ほど注目されにくいですが、父親からの過干渉も存在します。
父親の過干渉は、母親のそれと少し性質が異なることが多く、進路や学業、仕事の選択への強い介入として現れることがあります。たとえば「この大学に行け」「この職業に就け」「もっと稼げるようになれ」といった形で、子どもの将来設計を親の価値観で強くコントロールするケースです。

また、スポーツや習い事への口出しも典型です。「もっとこう練習しろ」「試合で失敗するな」といった強い干渉は、子どもの自主性を奪い、プレッシャーや萎縮につながることがあります。
父親が「家族を導く存在」としての責任感を強く持つあまり、無意識に過干渉になってしまうことが多いのです。その結果、子どもは「自分で選ぶ力」が育ちにくくなり、父親の顔色を気にして行動するようになってしまいます。
つまり、父親からの過干渉も確かにあり、その影響は母親のケースと同じように、大人になってからの自己肯定感や意思決定のスタイルに影響を与える可能性があります。
次:過干渉されて育っても……今からできる「立て直し方」