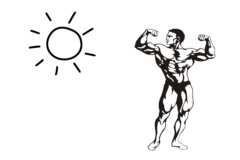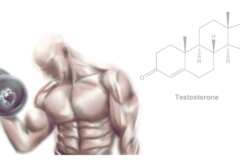繰り返し喉を鳴らす、ずっと咳払い…それ「大人のチック症」かも?対処法を専門家に聞いた (2/2)
「気になる」と感じる人は、どんな対処法をすればいい?
とはいえ、どうしても気になってしまう人もいるかと思います。その場合、環境調整や本人の負担を減らす工夫をすることが有効的です。
無理に我慢をしては、今度は周囲がストレスによって心身の不調を起こすこともあり得るので、以下のような対処法を試してみてください。
環境を工夫する
- ノイズキャンセリングイヤホンをつける、作業用音楽を聴く
- イヤホン禁止の場合、小型の加湿器(一定の音を出すもの)などを置き、気になる音をマスキングする
- できる限り場所を変えるなど、物理的に距離を取る
本人の背景を理解し、知識を持つ
チック症は本人の意思でコントロールが難しい症状です。「わざとやっているわけではない」と認識することで、イライラやストレスが軽減することもあります。
また、本人と会話を増やす、コミュニケーションをとることで、気にならなくなることもあります。
たとえば、同じ音を友人が出しているとイメージしてみてください。“知らない人” からの騒音はうるさく感じますが、“多少仲がいい人、嫌いではない人”からの騒音は、あまり気にしなくなる傾向はありませんか?
専門家の力を借りるよう促す
症状がひどい場合、本人が心療内科や神経内科に相談することで、認知行動療法や薬物療法を受けられる場合があります。
周囲が「専門家に相談してみるのはどう?」と優しく促すのも一つの方法です。
ただし、本人もすでに受診済みの可能性があるため、体調を気遣う形でさりげなく会話から探っていくのがよいでしょう。
専門家が考える、チック症との付き合い方
チック症は本人が自分にあった対処法を見つけ、無理せず向き合うことも大切です。症状を完全に止めるのは難しいですが、コントロールする工夫は可能です。
たとえば以下の対処法があります。
1. 前駆衝動(症状が起こる前の前兆)に気づき、深呼吸やストレッチなど別の行動に置き換えるとよいでしょう。
2. ストレスを軽減するために呼吸法・運動・瞑想を取り入れることが効果的です。
3. 「気にしすぎない」意識を持ち、自分を責めないことも大切です。
4. 症状がつらい場合は専門家に相談し、認知行動療法(CBT)や薬物療法を検討しましょう。
チック症と似た症状にはどんなものがある?
大人のチック症と間違われやすい疾患として、以下のようなものがあります。
トゥレット症候群
複数の運動チックと音声チックが同時に現れます。
強迫性障害 (OCD)
「喉を鳴らす」「動作を繰り返す」といった行動が、強迫観念に基づいて行われる場合も。
慢性咳嗽(がいそう)
長引く咳が無意識に繰り返される症状。喘息やアレルギー、胃酸逆流症などが原因になることがありますが、心理的な要因で咳や喉鳴らしが癖になるケースもあります。
副鼻腔炎やアレルギー疾患
鼻や喉の違和感から、音声チックに似た「鼻すすり」「喉を鳴らす」といった行動が習慣化することがあります。
ほか、パーキンソン病など、特定の神経疾患が原因で、顔の筋肉の動きや声帯に不随意運動が起こり、チック症状に似た症状が出る場合があります。
「イライラしても音は止まない」を受け入れる
大人のチック症と似た症状を引き起こす病気や状態には、精神的・身体的なものが複雑に絡んでいる場合が多いです。
単なる「クセ」や「習慣」ではなく、 本人も無意識に繰り返してしまう神経学的な症状です。症状が本人や周囲にとって負担となる場合は、専門家(心療内科や神経内科)に相談することが大切です。
また、周囲の環境やコミュニケーションの工夫によって、本人のストレスを軽減することが、結果的に症状緩和にもつながります。
もし身近な人がチック症で悩んでいる場合、 「無理に抑えなくて大丈夫だよ」 といった声かけや環境を調整することで、本人のストレスを減らし、チックの頻度を和らげるサポートができるでしょう。
監修者プロフィール
内田優子(うちだ・ゆうこ)
 大学で障害児教育を専攻し福祉職の実務経験を持つ。身体と心の健康に関する幅広い知識を生かし、現在はセラピストとしてサロン「ホルバール」にてオールハンド技術と最新美容を融合し、美と健康をサポート。福祉×美容の視点で“本質的な美”を追求し持続可能な美しさを提案。「美しさを根本から引き出すケア」を広めることを使命にしている。
大学で障害児教育を専攻し福祉職の実務経験を持つ。身体と心の健康に関する幅広い知識を生かし、現在はセラピストとしてサロン「ホルバール」にてオールハンド技術と最新美容を融合し、美と健康をサポート。福祉×美容の視点で“本質的な美”を追求し持続可能な美しさを提案。「美しさを根本から引き出すケア」を広めることを使命にしている。
<Edit:編集部>

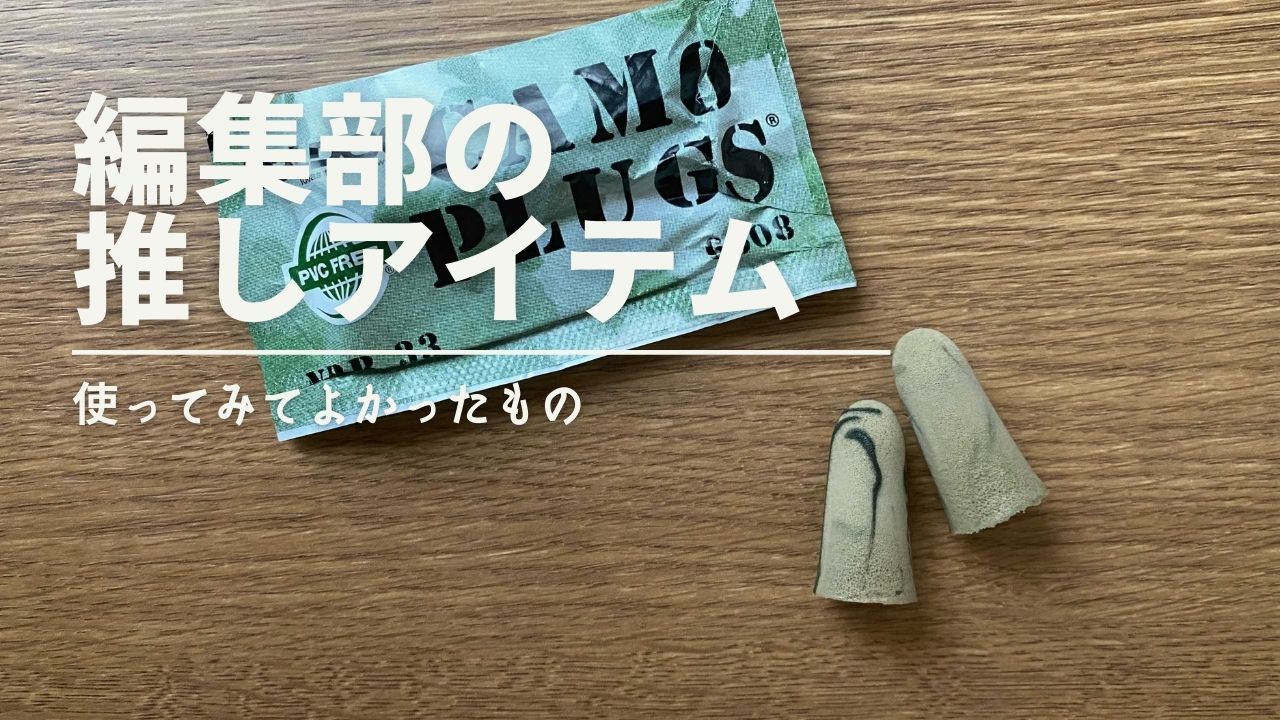 騒音対策に!最強耳栓「モルデックス カモプラグ」は超おすすめ|編集部の推しアイテム
騒音対策に!最強耳栓「モルデックス カモプラグ」は超おすすめ|編集部の推しアイテム 身近な人のメンタル不調、無理せず支えるための「10のヒント」
身近な人のメンタル不調、無理せず支えるための「10のヒント」