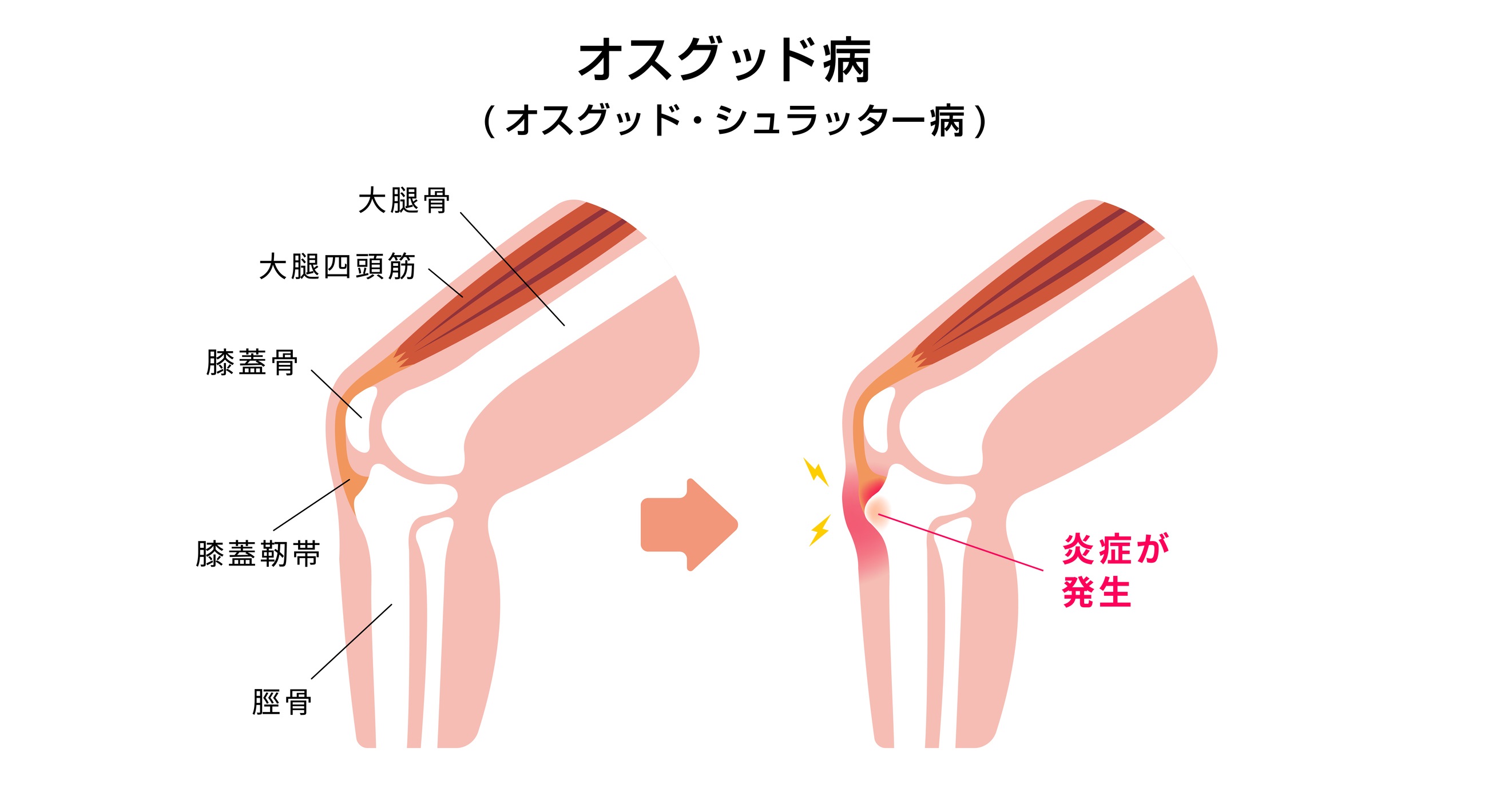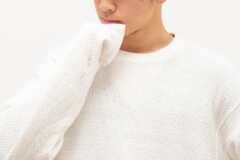過保護すぎ!過干渉な母親に育てられた人は、大人になってどんな影響が出やすい? (1/4)
過干渉な環境で育つと、その影響は子ども時代だけで終わらず、大人になってからも人間関係や自己肯定感、意思決定のあり方に色濃く残ることがあります。
母親の過干渉は、大人になった私たちにどんな影響を与えるのか。また、大人になってからも過干渉されている場合、どう対処するとよいのでしょうか。神谷町カリスメンタルクリニック院長の松澤美愛先生監修のもと、見ていきましょう。
どんな行動が「過干渉」にあたるのか?
「過干渉」とは、子どもが自分で考えたり選んだりする機会を奪い、親が必要以上に介入してしまうことを指します。具体的な行動の例としては、次のようなものがあります。
- 子どもの持ち物や服装、勉強方法まで親が細かく決めてしまう
- 子どもが失敗する前に先回りして口を出し、体験のチャンスを奪う
- 子どもの交友関係に過度に口を出し、会う相手や遊び方を制限する
- 子どもの意見よりも「親の考えが正しい」と押しつける
- 本人が望んでいない習い事や進路を強く勧める、または強制する
こうした行動は「子どものため」という気持ちから出ることも多いですが、度が過ぎると子どもの自主性や自己肯定感を育みにくくし、将来の人間関係や意思決定にも影響を及ぼす可能性があります。
母親から過干渉されて育った場合、成長するとどんな影響が出やすい?
母親から過干渉されて育つと、成長後の性格や人間関係にさまざまな影響が表れやすくなります。
自分で決断するのが苦手
まず多いのは、自分で決断するのが苦手になることです。
子ども時代に親が何でも決めてしまうと、自分で考えて選ぶ経験が不足し、大人になっても「どちらを選べばいいかわからない」「間違えたらどうしよう」と不安になりやすくなります。
自己肯定感が低い
また、自己肯定感の低さも目立ちます。常に「親に認められるかどうか」が基準だったため、自分の価値を自分で感じにくくなり、「どうせ自分なんて」と思い込みやすい傾向があります。
人間関係の距離感が掴みにくい
さらに、人間関係で相手に依存したり、逆に距離をとりすぎたりするケースもあります。
誰かに強く影響されるのが当たり前になっていた人は相手に依存しやすく、逆に「もう二度と干渉されたくない」という気持ちから、人と距離を置きすぎることもあります。
そのほか、完璧主義や強い劣等感、失敗を極端に恐れるなども過干渉の影響としてよく見られます。母親の過干渉は「自分で考えて行動する力」と「自分を肯定する力」を育ちにくくする可能性があると言えます。
次:なぜ父親より「母親」が過干渉になりやすいのか?

 幼少期、「親に甘えられなかった人」にはどんな特徴がある?大人になってからこんな“反動”も
幼少期、「親に甘えられなかった人」にはどんな特徴がある?大人になってからこんな“反動”も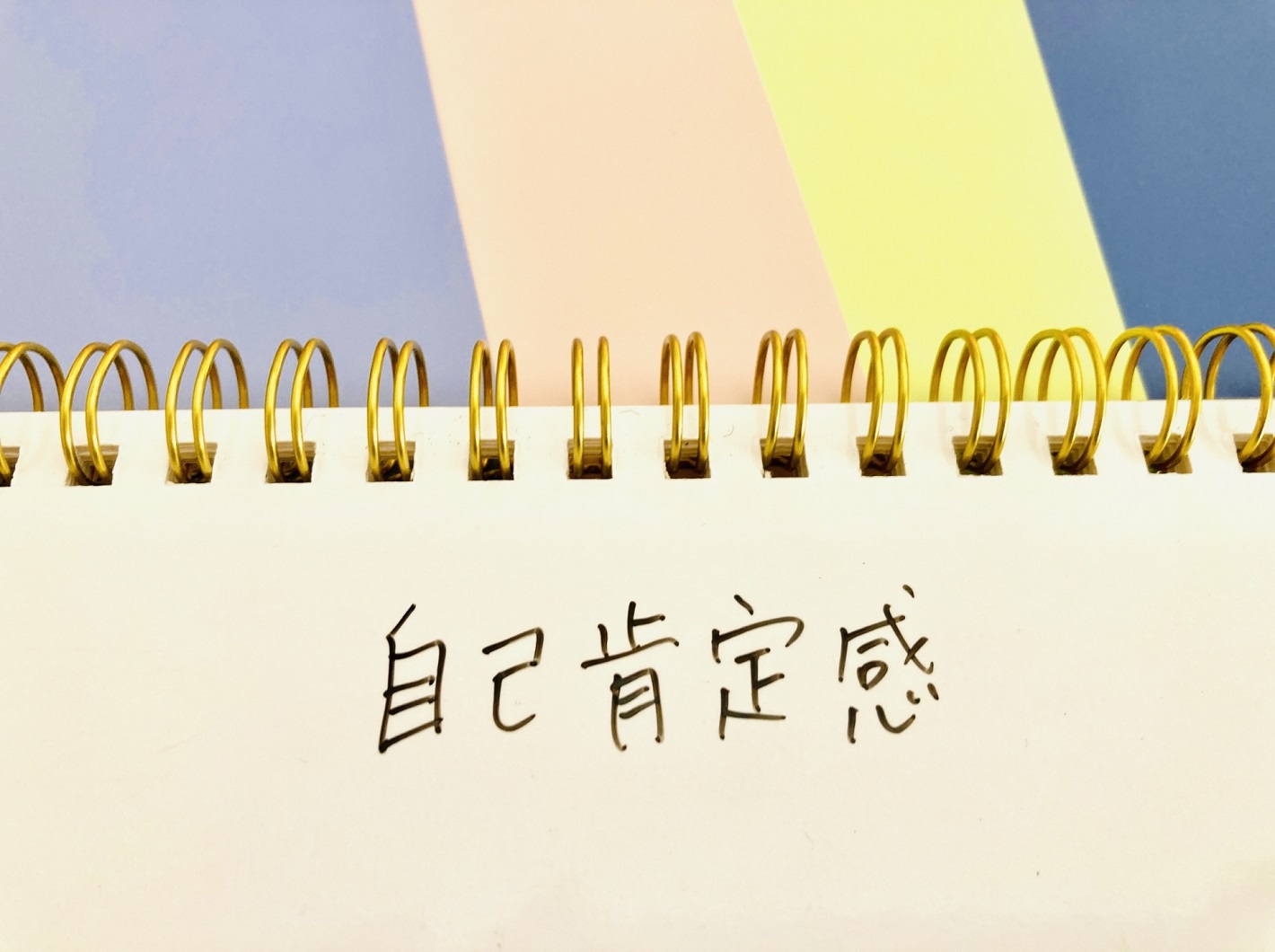 「自己肯定感が高い人は、他者も自分も大切にできる人」。心理専門家が考える、自己肯定感が高い人・低い人とは
「自己肯定感が高い人は、他者も自分も大切にできる人」。心理専門家が考える、自己肯定感が高い人・低い人とは