
ヘルス&メンタル
2025年4月16日
ADHDに“顔つきの特徴”はあるのか?表情や見た目に関する俗説と科学的見解 (2/3)
ADHDの特性が表情に影響を与えることはある?
ADHDの人の中には、以下のような表情や目の動きの傾向が見られることがあります。ただし、これらはあくまで一部の例であり、全ての人に当てはまるものではありません。
視線が不安定になる(目がキョロキョロする)
注意の持続が難しいため、視線が周囲を頻繁に移動することがあります。
表情が乏しく見える/急に変化する
感情のコントロールが難しい場合、表情の一貫性に欠けたり、突然変わったりすることがあります。
口が開きがちになる
注意散漫や低覚醒傾向、あるいは併存する鼻疾患や姿勢の影響により、一部の人において無意識に口が開いているように見えることがあります。(こうした傾向は特に子どもの場合に見られることが多く、成人ではあまり目立たないこともあります。)
顔の筋肉がこわばる、緊張して見える
過集中や不安によって身体がこわばることで、顔の動きも硬くなることがあります。
眠たそうに見える、まぶたが重く感じられる
注意力の低下や疲れやすさによって、表情にだるさが出ることもあります。
これらはあくまで一部のケースに見られる“行動傾向の副産物”であり、顔つきとは無関係です。
次:なぜそのような表情が現れるのか?

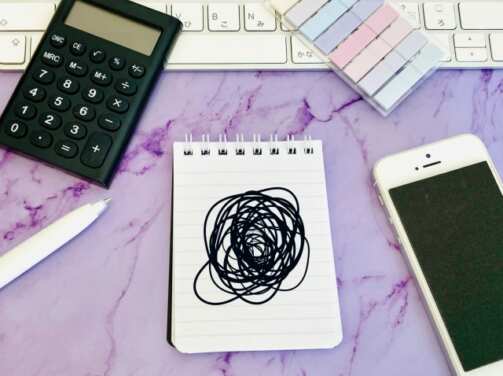 なぜADHDだと「頭がごちゃごちゃ」するのか?その理由と整理方法
なぜADHDだと「頭がごちゃごちゃ」するのか?その理由と整理方法





