
ヘルス&メンタル
2025年7月8日
医師が教える「自律神経を整える最強ルーティン」6選 (1/2)
「なんとなく疲れが取れない」「イライラしやすい」「眠りが浅い」、それは“自律神経の乱れ”が原因かもしれません。
イシハラクリニック副院長で、漢方医学や自然・食事療法が専門の石原新菜先生に聞いた、自律神経を整えるコツをお届けします(リンナイ『熱と暮らしの通信』より)。
石原先生直伝! 自律神経を整える6つのコツ
1. ストレスを感じたら「腹式呼吸」で副交感神経をオンに
– 鼻から吸って、口からゆっくり吐く
– 緊張や不安をリセットしやすくなる
– 1日数分でも効果あり
ストレスを感じたときには、腹式呼吸がおすすめです。鼻から息を吸って、口から時間をかけて吐くことで副交感神経が優位になりリラックスできます。
2. 腸を整えれば心も整う!発酵食品と食物繊維で“脳腸相関”をサポート
– セロトニンの鍵は腸内環境
– 発酵食品+食物繊維・オリゴ糖のセットが重要
脳と腸は密接につながっています(脳腸相関)。脳にストレスがかかることで、腸内環境も悪くなります。
また、腸内細菌が幸せホルモン「セロトニン」の合成に関わっていることから、腸内環境が悪いと逆に脳にも悪影響を及ぼします。
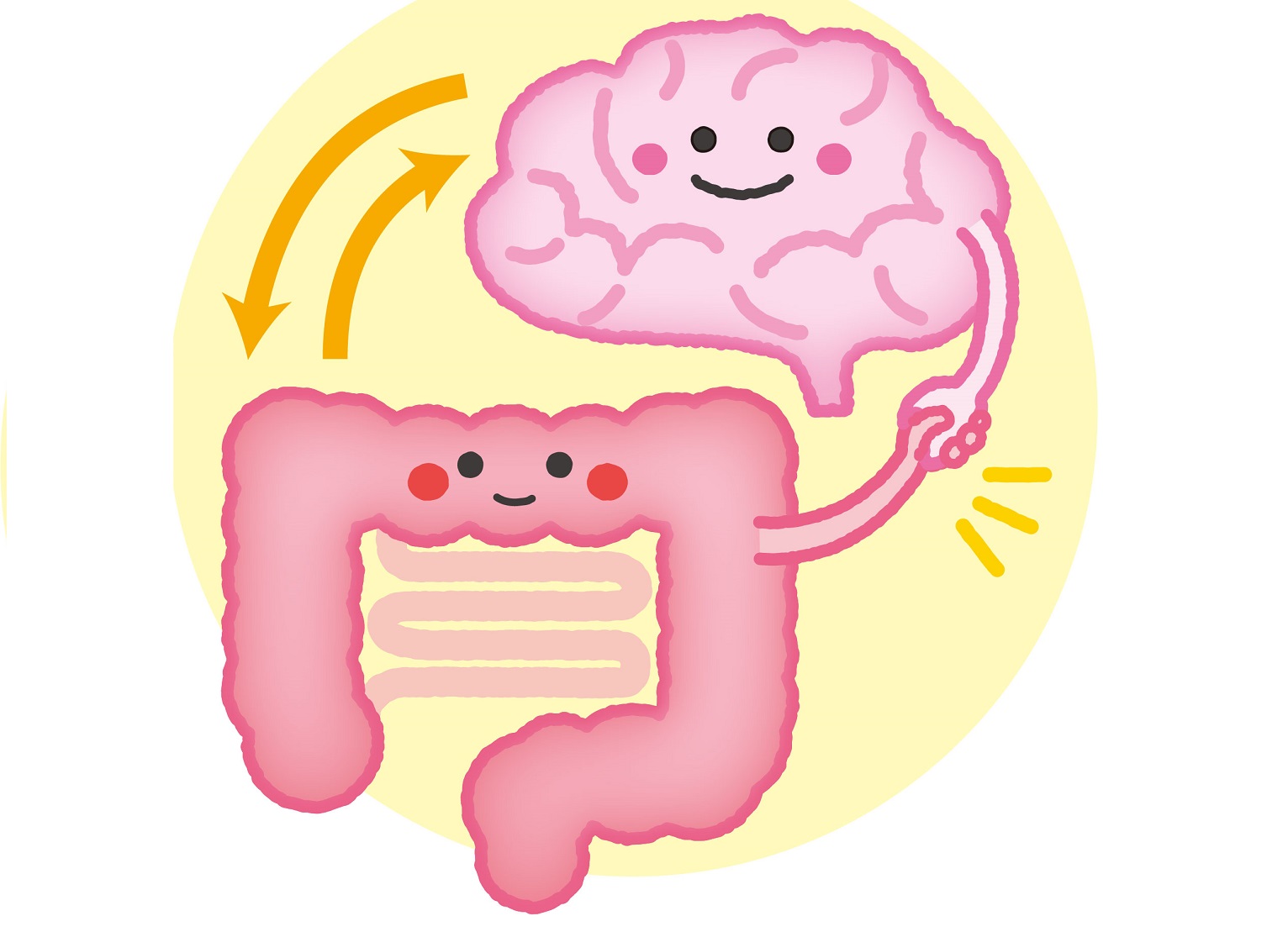
発酵食品、そしてその善玉菌が腸内で増殖していけるように、菌の餌になる食物繊維・オリゴ糖をとりましょう。
3. 自律神経は睡眠で回復。湯船に浸かって「質のいい夜」を
– 入浴は40℃のお湯に10分が目安
– シャワーだけでは不十分
– 睡眠の質が高まれば、日中の集中力・安定感もアップ
湯船につかることで、身体が温まり、睡眠の質向上が期待できます。お湯の温度が高すぎたり、長風呂しすぎたりすると、かえって冷えてしまうので、40℃のお湯に10分間の入浴を目安にしましょう。
しっかり寝ることで副交感神経が優位になって身体がリラックスし、自律神経が整います。
次:まだまだある!自律神経を整えるコツ&石原先生のリアル生活習慣
1 2

 最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]
最近よく聞く「自律神経」とは?自律神経が乱れる原因と整える方法[医師監修]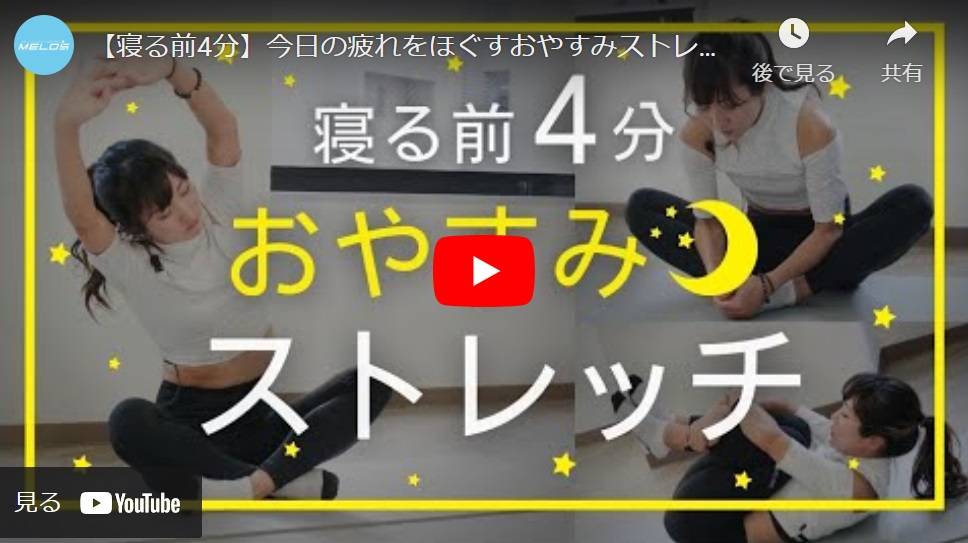
 ダイエットにおすすめの「発酵食品」一覧
ダイエットにおすすめの「発酵食品」一覧






