
「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは (1/2)
首都圏では中学受験ブームが続いており、小学生の5人に1人が中学受験をする時代となっています。2024年入試の受験率は過去最高を続伸し、多くの親子が進学への重圧に直面しています。
塾や習い事、受験対策と、わが子の将来を思って熱心に教育を施す親が増える中、「子どものため」と思って行う教育が、実は深い心の傷となって子どもを追い詰めているケースが増加しています。
子どもの神経発達の診療や研究の第一人者で、「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」の著者でもある、小児科医・高橋孝雄先生と、自身も幼少期から教育虐待を経験してきた映画監督・古新舜さんが、増加する"教育虐待"の実態に迫ります。
「子どものため」という思いが引き起こす静かな悲劇
「『教育はいいこと、虐待は悪いこと』という共通認識があるからこそ、『教育虐待』という言葉は強い違和感を与えるのでしょう。そして、その違和感こそが、実は問題の本質かもしれません」と高橋先生は指摘します。
「親には虐待をしているという認識がまったくありません。『子どものために』という強烈な善意に基づいているので、それが虐待行為だということに気付かないのです」と高橋先生は説明します。
4歳からの東大進学、その先にあった現実
4歳の頃から毎日「東大に行け」「勉強しろ」と両親から言われ続け、自分の夢や希望を聞かれることもなく、「とにかく偏差値75」という世界で生きてきたと語ります。
親の方針で幼少期から進学塾に通い、東京大学を目指して英才教育を受けてきましたが、小学校から高校までずっといじめを受けてきたといいます。大学受験では東大に不合格。それを機に引きこもり、自殺を考えたこともあったそうです。
「両親も、私を思ってのことだったと今では分かります。でも、当時の私には『なぜ自分の気持ちを全く聞いてくれないのか』という深い孤独感しかありませんでした。その結果、心を病んでしまったんです」と古新さんは当時を振り返ります。
小児科医が警鐘を鳴らす「教育熱心」の落とし穴
「愛し、信頼する子どもに何かを託すことはいいことだと思います。ただ、自分の失ったものを子どもに取り返させよう、社会に対して子どもを代理としてリベンジしようとしているのなら、その思いを託す相手は子どもではありません」と高橋先生は指摘します。
「子どもがどう感じたかで決まります。10年後、20年後、30年後に『あれは辛かった、ひどすぎる』と思い返したとしたら、“あれ”は教育虐待だったと言えます。ただ問題は、虐待を受けている時点では、子ども自身もそのことに気付いていないということです。お父さんやお母さんは自分のことを思ってくれているのだと、虐待という概念すらないのが本当に切ない」と高橋先生は語ります。
次:専門家が提案する新しい親子関係の築き方

 子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法
子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法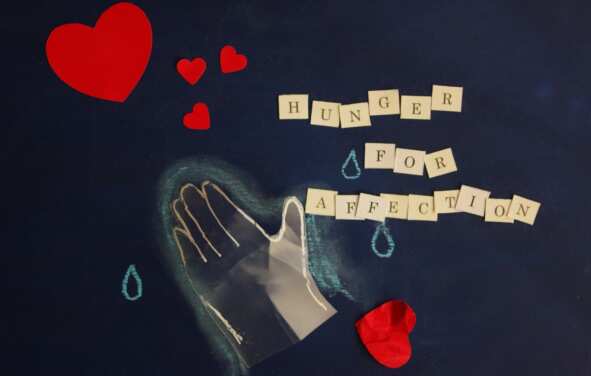 「親からの愛情不足で育った大人」の特徴とは。こんな問題行動や思考の偏り、ありませんか?
「親からの愛情不足で育った大人」の特徴とは。こんな問題行動や思考の偏り、ありませんか?







