
医師に聞いた、いびきをすぐに止める方法!ちなみに危険ないびきの特徴は… (2/2)
いびきを予防するための生活習慣
荒牧先生:心がけると、いびきの予防につながる5つの生活習慣を紹介します。
その1 鼻呼吸のくせをつける
鼻呼吸は口呼吸に比べ、綺麗な空気を体に取り入れやすく、いびき予防になります。
「あいうべ体操」で鼻呼吸を身につける
口角周辺の筋肉が衰えていると口が開きやすく、口呼吸になっていびきの原因となります。口輪筋や舌筋を鍛える「あいうべ体操」をすることで、鼻呼吸になりやすくなります。
「あいうべ体操」のやり方
1、「あ」の形で口を大きく開く
2、「い」の形で口を大きく開く
3、「う」の形で口を大きく開く
4、「べー」と舌を下に突き出す
 1~4の流れを、1日30セットを目安に行いましょう。※無理のない範囲で行ってください。
1~4の流れを、1日30セットを目安に行いましょう。※無理のない範囲で行ってください。
その2 暴飲暴食をしない
暴飲暴食は首や喉まわりにも脂肪がつき、気道を狭くして、いびきの原因となります。
その3 お酒を飲み過ぎない
お酒の飲み過ぎはアルコールによって全身の筋肉がゆるみ、喉の筋肉もゆるんで気道がせまくなりいびきの原因となります。
お酒は個人差がありますが、次を目安に留めておきましょう。
ビール:中瓶1本まで
日本酒:1合まで
チュウハイ(7%):350mL缶1缶まで
ワイン:グラス1~2杯(150~250ml)まで
その4 禁煙をする
喫煙により鼻粘膜が炎症を起こしやすい状態となり、気道がせまくなっていびきの原因となります。禁煙をすることで、炎症予防となり、いびきの改善や予防につながります。
その5 疲れをため込まない
疲れによって筋肉が緩み、口呼吸となっていびきの原因となってしまいます。
「睡眠時間を7時間ほど確保する」、「休日は趣味を楽しむ」、「ゆっくりお風呂に浸かる」などをしてリフレッシュの時間を作りましょう。
医師が考える、危険ないびきの特徴とは
荒牧先生:いびきだけでは問題ないのですが、無呼吸を伴う場合は危険です。
※無呼吸・・・10秒以上呼吸が停止してしまう状態
無呼吸は、眠りによって筋肉の緊張が解け、気道が塞がれるために起こります。呼吸が苦しくなるだけでなく、心臓、脳、血管などに負荷をかけて心臓病や糖尿病といった命に関わる病気を引き起こすことがあるため、十分注意が必要になります。
睡眠時無呼吸症候群の疑いも
睡眠時無呼吸症候群とは、いびきに無呼吸を伴う状態を指します。
睡眠中に「無呼吸状態が1時間に5回以上」「無呼吸状態が7時間の睡眠中に30回以上」がみられる場合、「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。
この病気になると、低酸素状態になって息が苦しくなるため、体が生命の危機を感じて瞬間的に覚醒状態にうつります。覚醒状態によって気道周囲の筋肉の緊張がもとに戻り、呼吸も戻ったときにいびきが出ます。
放置するとこんなリスクが!
睡眠時無呼吸症候群の場合、睡眠時も交感神経が緊張した状態も続きます。これにより、高血圧・高血糖の状態となり、心臓病や糖尿病といった重い病気を招く恐れがあります。
また、無呼吸症状がある人は、睡眠で十分に休めないので、日中に疲れが出て眠気が生じることがあります。特に車を運転する人は事故につながるケースもあるので、注意が必要です。
無呼吸のいびきでお悩み場合は、放置せず内科で治療を受けましょう。
いびき治療は保険適用、内科で相談を
荒牧先生:いびき治療には保険適用がされるため、病院での相談をおすすめします。
・無呼吸の症状がある
・家族にいびきを指摘された
・日中に強い眠気を感じる
上記のような場合は、早めに受診しましょう。医療機関で治療を受けることで、症状がより改善しやすくなります。まず内科で相談してみましょう。
病院のいびき治療、どんなことをするの?
荒牧先生:病院のいびき治療は次のようなものがあります。
1、鼻CPAP(シーパップ)
鼻CPAPは酸素マスクを装着して休む治療方法です。接続した機械からマスクに酸素が送りこまれるのですが、その酸素が気道を開き、無呼吸やいびきを予防します。
中等から重症の無呼吸症治療には有効で、医療機関を受診しながら根気よく治療を続けるといびき症状が緩和していきます。
2、マウスピース
無呼吸症状が軽度のときの治療法です。専用のマウスピース(口腔内装置)を作り、休むときにはめます。
マウスピースはほんの数ミリ、上あごが前に出るように装着します。そうすると舌の根が気道をふさぐのを防ぎ、酸素がスムーズに送り込まれるようになります。
3、外科的手術
扁桃肥大が原因の無呼吸症を根本治療するときは、摘出手術など外科的手術を行うこともあります。症状の度合いにもよりますが、扁桃肥大には摘出手術が適しているので、医師によくご相談ください。
4、体位治療
あおむけに休むより横向きのほうが気道の狭窄(きょうさく)が起きにくくなります。無呼吸症の状態や原因に合わせ、抱き枕など横向きになって休むようなサポート器具を用いることがあります。
監修者プロフィール
荒牧内科 荒牧竜太郎院長
 経歴
経歴福岡大学病院
西田厚徳病院
平成10年 埼玉医科大学 卒業
平成10年 福岡大学病院 臨床研修
平成12年 福岡大学病院 呼吸器科入局
平成24年 荒牧内科開業
<Edit:編集部>
※本記事は、Medicalook(メディカルック)で掲載されていた内容を移管し、加筆・修正したものです。

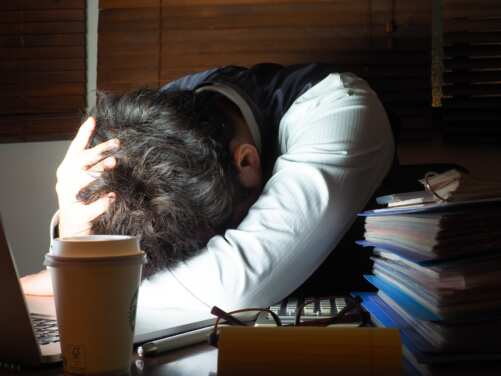 心療内科医に聞く「やってはいけないストレス解消法」ワースト3
心療内科医に聞く「やってはいけないストレス解消法」ワースト3







