
「親からの愛情不足で育った人」の特徴とは?愛情たっぷりに育てられた人との違い
あなたの身近に、「自己肯定感がとても低い」「距離感が独特」「ちょっとした一言で傷ついてしまう」──そんな印象を受ける人はいませんか? もしかするとその背景には、幼少期の環境が関係しているかもしれません。
親からの十分な愛情や承認を受け取れずに育った人は、大人になってからも人との関わり方や自己肯定感に影響を抱えていることがあります。
そういった人たちには、どんな特徴が見られやすいでしょうか。また、愛情たっぷりで育った人との違いとは。専門家の意見をまとめていきます。
「愛情不足で育った人」とはどういう状態か
監修者プロフィール
神谷町カリスメンタルクリニック院長
松澤 美愛先生
東京都出身。慶應義塾大学病院初期研修後、同病院精神・神経科に入局。精神科専門病院での外来・入院や救急、総合病院での外来やリエゾンなどを担当。国立病院、クリニック、障害者施設、企業なども含め形態も地域も様々なところで幅広く研修を積む。2024年東京都港区虎ノ門に「神谷町カリスメンタルクリニック」を開業、院長。精神保健指定医/日本精神神経学会/日本ポジティブサイコロジー医学会
URL https://charis-mental.com/
InstagramURL https://www.instagram.com/charismentalclinic
「愛情不足で育った人」とは、幼少期に親や養育者から十分な愛情・安心感・肯定的な関わりを得られなかったことで、心に深い影響を残している人を指します。
心理学では、乳幼児期の親子関係を通じて育まれる心の土台を「愛着(アタッチメント)」と呼びます。親が一貫してあたたかく、安心を与える存在であった場合、子どもは「人は信頼できる」「自分は愛される存在だ」と感じるようになります。
子どもが親を求め、親も子どもを求める、ここに双方向の相互関係・情緒的な絆が生まれます。

しかし逆に、親が感情的に不安定だったり、無関心、あるいは過干渉だった場合には、不安定な愛着スタイルが形成されやすくなります。
これが大人になってからの人間関係、恋愛、自己理解にまで影響するのです。
親からの愛情が不足して育ってきた人には、どんな特徴が見られる?
監修者プロフィール
三凛さとし
親子関係心理学の専門家・合同会社serendipity代表。夢を追って渡米したものの借金苦と活動の失敗によりホームレス寸前の生活に。「何かおかしい」と感じ、心理学や自己啓発を勉強する中で、人生を好転させる方法を習得。お金、時間、場所、人間関係、心身の健康(人生の5大自由)を実現するということをテーマに2014年より各SNSにて情報発信。2022年にはKADOKAWAより親子関係心理学についての書籍「親子の法則」を出版し、発行部数6万部を記録。2024年9月にはメンタルからお金の問題を解消する「金のなる本 誰でも再現できる一生お金に困らない方法」を発売。ABEMA TV -For Japan- 日本を経営せよ!、テレ玉「BOSSのプレゼン」など、メディア出演多数。
親から十分な愛情を受けずに育った人には、おもに以下の特徴が見られることが多いようです。
多くの面において自己肯定感が低い
自分を価値ある存在として認識するのが難しいため、自信を持てない、自分を過小評価しがちです。
対人関係が不安定になりやすい
愛情を受けた経験が多くないため、他者との親密な関係を築くことが苦手で、依存的になったり逆に距離を取り過ぎたりします。
感情のコントロールが苦手である
感情のコントロールが苦手で、ストレスや不安に対して過敏に反応する、過度に喜ぶなど感情的になりやすいです。
よく見られる思考の偏り
「他人の評価がすべて」
親からの肯定を得られなかったことで、他者の評価に依存しがちで、自分自身の評価基準を持つのが難しくなります。人は多少なりとも他者の評価で生きている部分はありますが、愛情不足で育った人は、大部分を他者評価に委ねてしまいがちです。
「自分は愛される価値がない」
幼少期に愛されなかったという経験から、自分は愛されるに値しない存在だと思い込み、「どうせダメ」など自らの可能性を制限することが多いです。
「完璧でなければならない」
他人に認められるために、自分を完璧であるべきだと強く思い込み、失敗や不完全さを極端に恐れる傾向があります。
愛情不足の影響が深い場合、こんな問題行動や課題が起きやすい
必ずしもすべての人に当てはまるわけではありませんが、愛情不足の影響が深い場合、以下のような傾向が現れやすいです。
対人関係における問題
愛情不足で育つと、他者との絆や信頼感を築くのが難しくなりやすいと言われています。過度な依存や試し行為、頻繫な人間関係リセットなどが見られることも。
反対に、親からの無条件の愛情を受け取れなかった経験が原因で、人との深い関わりを避ける「回避的な態度」が形成されることもあります。
他人に心を開くことを恐れ、孤立を選ぶ場合が多く、結果的に孤独感が増してしまいます。
感情コントロールが苦手
子どもの頃に親から感情を否定された、無視された経験があると、感情を健全に表現する方法を学べないことがあります。
怒りや悲しみ、不安などの感情を適切に表現できず、ストレスが溜まりやすくなります。爆発的な怒りや、逆に感情を抑え込み過ぎて無気力になることも。
感情を長期間にわたって抑え込むことで、ある時点で感情が爆発することもあります。些細なことで激怒したり、過剰に悲観的になったりするなど、感情のコントロールが効かなくなる場合があります。
自己肯定感が低く、挑戦できない
愛情不足で育った人は、自分の価値を他者からの評価に依存しがちです。
親からの無条件の愛情を経験していないため、「自分は愛されるに値しない」「どうせダメ」と感じることが多く、自己肯定感が低くなる傾向があります。これにより、チャレンジ精神の欠如や失敗への恐怖として現れることがあります。
依存気味、相手をコントロールしようとする
愛情を求めて他人に過剰に依存する傾向があり、執着やコントロール欲求を持ちやすくなります。恋愛や友情で相手に過剰に期待し、少しの不安や疑念で相手に対する信頼を失うことがあります。
また、自分と他者の境界が曖昧になりがちで、相手の感情や意見を過度に受け入れてしまうか、逆に自分の感情を押し付けることがあります。
反社会的・攻撃的な行動をしてしまう
愛情不足からくるフラストレーションや寂しさが、攻撃的な行動として現れることがあります。
とくに、親や上司といった権威者に対する反抗的な態度や、自己防衛として周囲に対して攻撃的になる傾向が見られることがあります。
アルコールやギャンブル依存症などリスクが高い行動を行う
アルコールや薬物に頼る、過度なギャンブルに走るといったリスクの高い行動を取ることがあります。
これらは、心理的な不安定さや空虚感を埋めようとする自己破壊的な行動の一環です。
完璧主義や過度な自己批判
条件つきの愛情しか与えられなかった場合、完璧でない自分を許せないという思考パターンが形成されることがあります。
常に「もっと努力しなければ」「自分はまだ不十分だ」と考え、失敗やミスに対して過剰に自分を責める傾向があります。
親や他者の期待を満たそうとする完璧主義思考により、心身に大きな負担がかかこともあります。
不安障害や人格障害、うつ病のリスク
愛されなかった経験が「自分は価値がない」という根本的な感覚を植え付けてしまい、それによる問題行動や課題により不安障害や人格障害、うつ病といったリスクが高まることがあります。
両親から愛されて育った人とそうでない人、どんな違いがある?
監修者プロフィール
城西内科クリニック院長
髙橋 聡美先生
順天堂大学医学部卒業、医学博士
順天堂大学練馬病院糖尿病内分泌内科助教
糖尿病認定医、臨床栄養学会認定栄養指導医、内科学会認定内科医
統合医療医、日本医師会認定健康スポーツ医
両親からたっぷりと愛情を受けて育った人と、さまざまな事情で愛情が不足した環境で育った人では、大人になってからの考え方や行動パターンに違いが見られることがわかっています。
これは決して「愛されなかった人はダメ」という話ではありません。むしろ、なぜ自分がこういう考え方をするのか、なぜこんな行動パターンになりやすいのかを理解することで、より生きやすくなるヒントが見つかるかもしれません。
両親の愛情を受けて育った人に見られる3つの特徴
まずは、両親から愛情をしっかりと受けて育った人に共通して見られる特徴について見ていきます。
自分を信じる力と心の安心感がある
愛情を受けて育った人の最大の特徴は、自己肯定感の高さと基本的な安心感です。
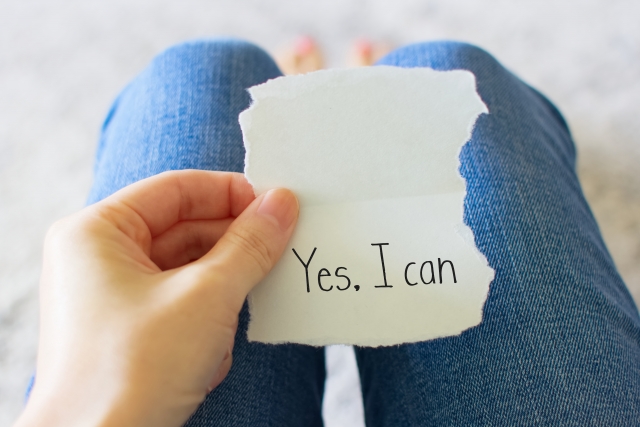
幼少期に「あなたは大切な存在だ」というメッセージを繰り返し受け取ることで、「自分には価値がある」という感覚が心の土台として形成されます。
これは「自分は完璧だ」という意味ではなく、「欠点があっても、失敗しても、自分という存在は受け入れられる」という深い安心感です。
この土台があると、新しい環境に飛び込むときや困難に直面したときでも、「何とかなる」「最悪の場合でも自分は大丈夫」という感覚を持つことができます。過度に不安になったり、自分を責めすぎたりすることが少ないのです。
また、他人の評価に一喜一憂しにくいという特徴もあります。もちろん褒められれば嬉しいし、批判されれば落ち込みますが、それによって自分の価値が根本から揺らぐことはありません。
「この人はこう思っているんだな」と、他人の意見を参考にしつつも、最終的には自分の判断を信じることができるのです。
適切な距離感を保ち、必要なときに助けを求められる
愛情を受けて育った人は、人との境界線を引くのが上手です。
ここでいう境界線とは、「自分と他人は別の人間である」という当たり前のようで難しい認識のこと。相手の問題を自分の問題として背負い込みすぎることなく、また自分の問題を他人に丸投げすることもなく、適度な距離感を保てます。
「それは私の責任ではない」「これは手伝ってほしい」といった判断を、罪悪感なく行うことができるのです。人に頼ることを「弱さ」ではなく、「上手な協力の仕方」として捉えられます。

困ったときに「助けて」と素直に言えるのも大きな特徴です。幼少期に「困ったら頼っていいんだよ」という経験を重ねているため、助けを求めることに抵抗がありません。
一方で、相手が「NO」と言う権利も尊重できるため、断られても過度に傷ついたり、関係が壊れたりすることも少ないのです。
失敗を恐れず、経験として前に進める
愛されて育った人は、失敗への恐怖が比較的少ない傾向があります。これは「失敗しても、自分の価値が否定されるわけではない」という感覚があるからです。
幼少期に失敗したときも、親から「だめな子だ」と否定されるのではなく、「次はどうする?」と一緒に考えてもらった経験が土台になっています。
そのため、新しいことに挑戦するハードルが低く、たとえうまくいかなくても「いい経験だった」「次に活かそう」と前向きに捉えられます。完璧主義に陥りにくく、「やってみなければわからない」というスタンスで行動できるのです。
もちろん失敗すれば落ち込みますが、その落ち込みが長期化したり、「自分は何をやってもダメだ」という極端な思考に発展したりすることは少ないでしょう。
失敗を「自分という人間の価値」と結びつけず、「今回の出来事」として切り分けて考えられるのです。
愛情が不足した環境で育った人に見られる3つの傾向
次に、さまざまな事情で愛情が不足した環境で育った人に見られやすい傾向について見ていきます。
断れずに無理をして、心身ともに疲弊しやすい
愛情不足の環境で育った人は、「NO」と言うことに強い罪悪感や恐怖を感じることが多いです。
幼少期に、自分の意見や感情を表現しても受け止めてもらえなかった、あるいは否定された経験があると、「自分の気持ちよりも相手の期待に応えることが大切」という思考パターンが形成されます。
その結果、無理な頼みごとを引き受けてしまったり、本当はやりたくないことに「いいよ」と言ってしまったり。相手を優先しすぎて、自分の限界を超えてしまうのです。
これを心理学では「過剰適応」と呼びます。

周囲からは「優しい人」「頼れる人」と評価されることも多いのですが、本人は常に疲弊していて、心身のバランスを崩しやすくなります。
断ることで「嫌われるのではないか」「見捨てられるのではないか」という不安が根底にあるため、自分を犠牲にしてでも相手の要求に応えようとしてしまうのです。
他人の評価に左右され、自己評価が揺らぎやすい
愛情不足で育った人は、自分で自分の価値を決められない傾向があります。
幼少期に無条件の愛情を受け取る経験が少ないと、「自分には価値がある」という感覚が育ちにくくなります。代わりに、「何かができたら」「誰かに認められたら」価値があると考えるようになるのです。
そのため、他人からの評価や承認に敏感になります。褒められると天にも昇る気持ちになり、批判されると地の底に落ちたような気分になる。
この振れ幅の大きさが、日常生活を非常に疲れるものにしてしまいます。
また、SNSの「いいね」の数に一喜一憂したり、誰かと比較して自分を卑下したりすることも多くなります。「ありのままの自分」ではなく、「評価される自分」を演じ続けなければならないため、常に緊張状態にあるのです。
人との距離感がつかめず、人間関係に悩みやすい
愛情不足の環境で育つと、人との適切な距離感がわからないことがあります。
極端に距離を詰めすぎて依存的になったり、逆に極端に距離を取って孤立したり。この両極端を行ったり来たりすることもあります。「見捨てられるのが怖いから離れない」と「傷つくのが怖いから近づかない」が同時に存在し、人間関係が不安定になりやすいのです。
また、過度に警戒心が強くなることもあります。幼少期に信頼していた人(親)から傷つけられた経験があると、「人は信用できない」という思い込みが形成されます。
相手の何気ない言動を深読みしたり、悪意があるのではないかと疑ったり。あるいは逆に、境界線が曖昧すぎて、相手の問題を自分の問題として背負い込んでしまうこともあります。
「相手が困っているのに助けないのは冷たい」「相手が不機嫌なのは自分のせいだ」と考え、他人の感情に責任を感じすぎてしまうのです。
<Edit:編集部>

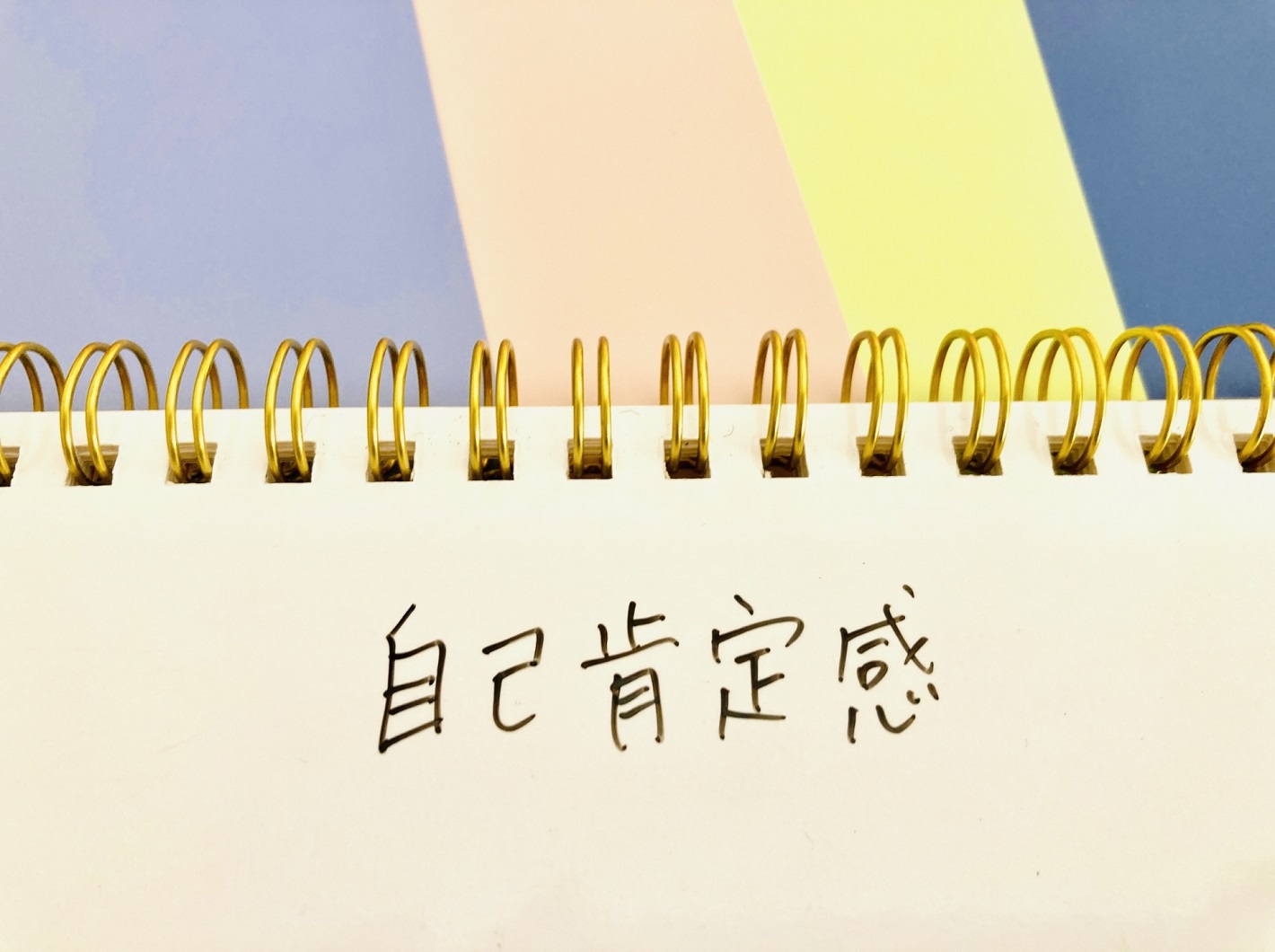
 辛い時、「悩みを相談できる人」がいない。誰かに話を聞いてほしい…どう切り抜ける?
辛い時、「悩みを相談できる人」がいない。誰かに話を聞いてほしい…どう切り抜ける? 【専門家監修】なぜ愛着障害があると恋愛で悩みやすい?その理由と、今日からできる対処法
【専門家監修】なぜ愛着障害があると恋愛で悩みやすい?その理由と、今日からできる対処法

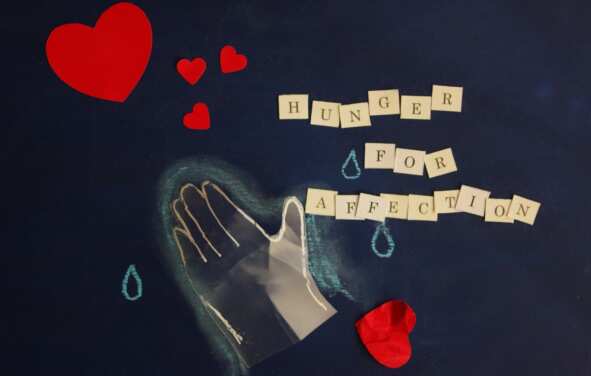

 続き:
続き:







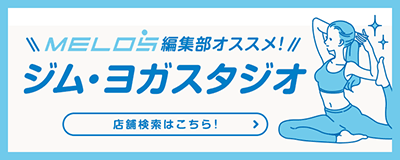



![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)

![懸垂を毎日続けるとどうなる?「1日5回」でも体は変わる[トレーナー解説]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2025/12/27153658/image007-240x160.jpg)



