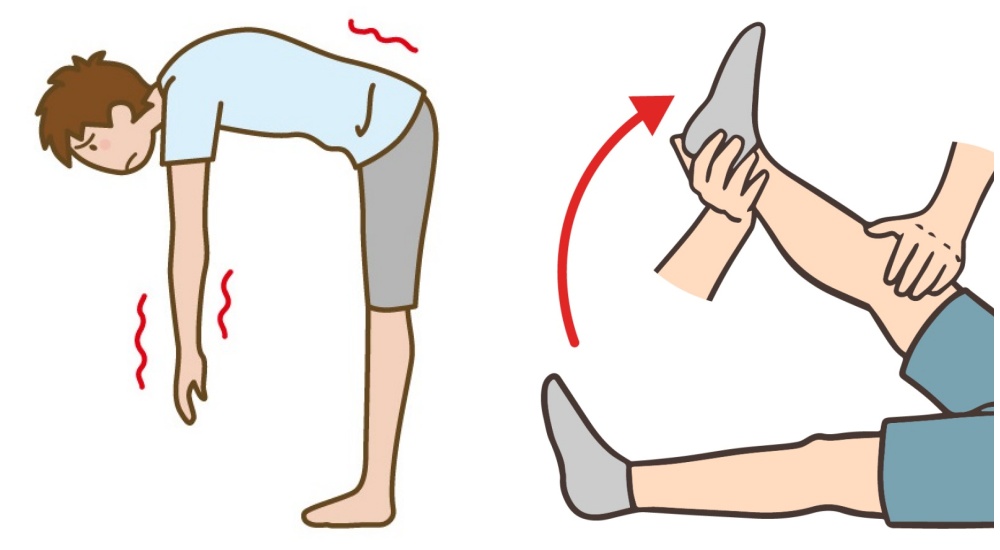ライフスタイル
2024年6月20日
子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法 (2/3)
いま重視されている「非認知能力」とは
新学習指導要領により、平成30年度から順次、教育が変わっていきます。とくに、幼児教育において「非認知能力」を育てていきたいという内容になっています。
非認知能力とは、学力のように数字にできない力を指しています。
裏を返せば、過去には身についているはずだった非認知能力が身についていない現状があるということです。
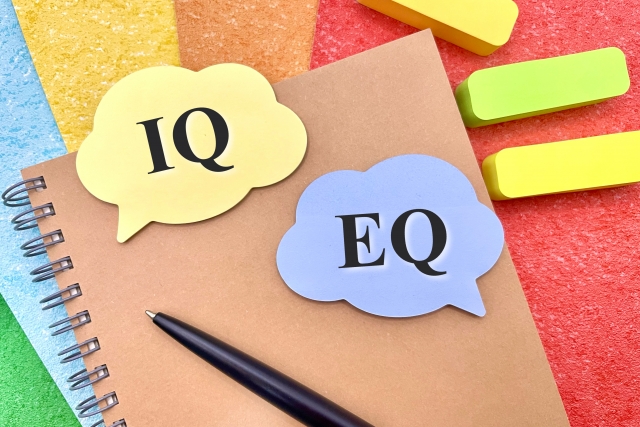
非認知能力とは、一体どんな力を指すのでしょうか。
非認知能力とは
非認知能力は「粘り強さ」「協調性」「やり抜く力」「自制心」「感謝する力」などを指し、それらは以下の3つに分類されるとしています。
1)目標に向かってやり抜こうとする力
2)感情をコントロールする力
3)人と上手にコミュニケーションを取る力
例:サッカーが上手ではなく、試合に出ることができない
具体的な例として、「サッカーが上手ではなく、試合に出ることができない」としましょう。
それでも、たとえば次のような成長が見られるのであれば、サッカーの練習をしてきた価値があるのではないでしょうか。
- サッカーが好きで楽しんで練習を行っている
- もとは嫌いだったが真剣に取り組むようになった
- 自分なりに工夫している
- うまくいかなくても、相手に負けてもイライラせずに、次に向けて気持ちを整理できる
- まわりの人にアドバイスを聞きながら練習できる
- コーチの話をしっかり聞き、感謝の気持ちを持てる

練習を積み重ねてきたからこそ、これらの力が身についたり、成長が見られるようになっていきます。
たとえ他人より下手でも、あるいは試合に出られなくても、このような力や気持ち、考え方が身についたり、その方向に向かったりしているのであれば、今後の人生において大きな財産を得たといえるでしょう。
次:現状は非認知能力が育まれにくい状態である

 「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは
「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは