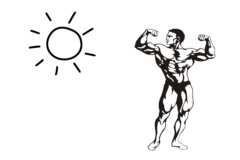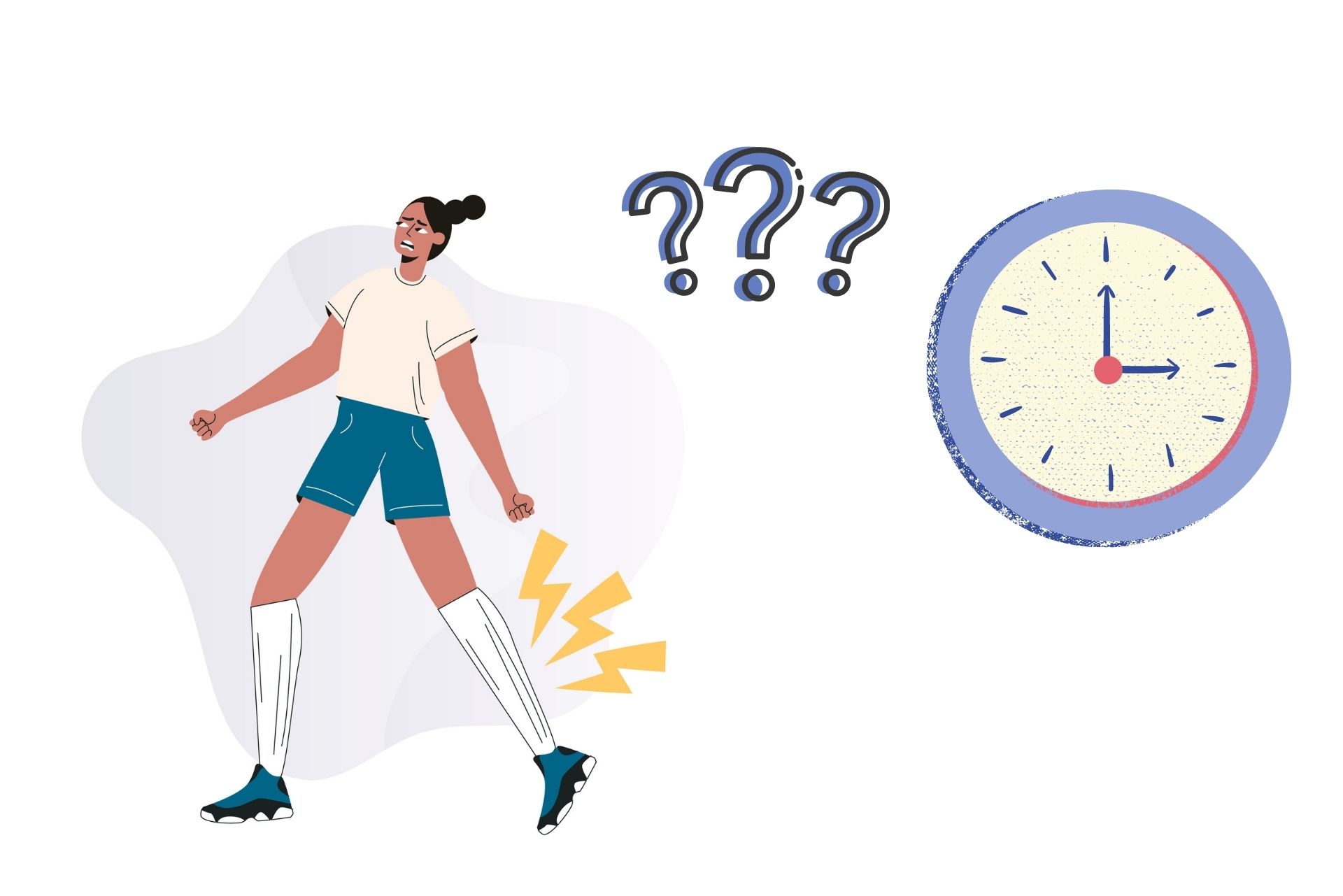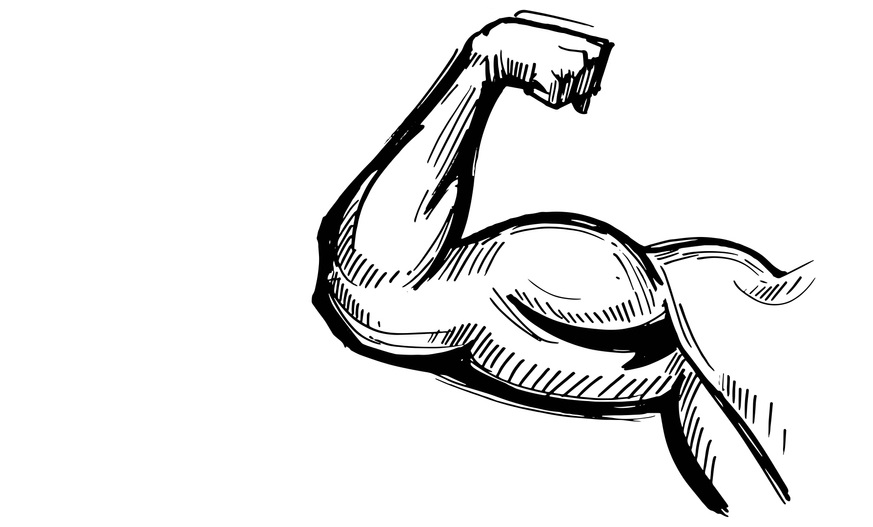なぜ筋トレが熱中症予防に効くのか?その理由と“体が暑さに勝つ”メカニズム (1/3)
筋トレで大量の汗をかく筋トレ民。もちろんトレーニング中の水分補給には余念がないことと思いますが、熱中症が心配されるこの季節、熱中症の知識と予防法はぜひ知っておきたいもの。
しかも筋トレが予防にひと役買っているというのです。
熱中症とその予防法、また、筋トレと熱中症の意外な関係について、国立がん研究センター研究所がん幹細胞研究分野長を務める医師・増富健吉先生に解説いただきます。
筋トレを趣味とし、得意分野という増富先生。がん幹細胞の研究のみならず、ご自身の筋肉細胞の研究にも余念がない筋トレ民です。
<このページの内容>
熱中症とは。原因と症状
そもそも熱中症とは、どのような症状をいうのでしょうか? まず、「熱中症という病気の本質」を理解すれば熱中症の問題点の多くの解決につながると増富先生。
「熱中症とは『暑熱環境下での急性の循環不全』です。医学用語はわざと難しくなっているので、かみ砕いて説明します」(増富先生)
熱中症=気温が高い環境下で血管内の水分不足、または体内に回らない状態(急性)
つまり、気温が高いことが原因(暑熱環境下)で、短時間に起こる(急性の)【1:血管内の水分の不足状態】、ないしは【2:血管内には水分はあるが、効率的に体内に回らない状態(循環不全)】が熱中症とのこと。
「【1】の代表が脱水。【2】は少し難しいのですが、迷走神経反射による脳貧血(脳に効率的に血液が回せなくなる)などの状態です。校庭での朝礼や、満員電車で気分が悪くなってしゃがみ込むとか、ぶっ倒れちゃう人を見たことありますよね。あのような症状が“暑さが原因”で起こる状態です」(増富先生)
熱中症の症状としては、初期には汗の出すぎや生あくび、動悸、めまい、立ちくらみ、頭痛、気分が悪い、立っていられないなど。さらに症状が進むと汗が出なくなり、受け答えがはっきりしない(意識障害)場合やカラダが非常に熱い場合は危険な状態といえるのだそうです。

以下は、熱中症の症状と重症度の分類です。
- Ⅰ度:現場での応急処置で対応できる軽症
立ちくらみ(脳への血流が瞬間的に不十分になったことを示し、熱失神とも)、筋肉痛、筋肉の硬直(発汗に伴う塩分の不足で生じるこむら返りで、熱けいれんとも)、大量の発汗
- Ⅱ度:軽症病院への搬送を必要とする中等症
頭痛、吐き気、嘔吐、下痢、倦怠感・虚脱感(カラダがぐったりする、力が入らないなど、熱疲労や熱疲弊といわれていた状態)、気分の不快、判断力の低下
- Ⅲ度:入院して集中治療の必要性のある重症
意識障害(呼びかけや刺激への反応がおかしい)、けいれん(カラダにガクガクとひきつけがある)、手足の運動障害(真直ぐ走れない、歩けない)、高体温(カラダに触ると熱く、いわゆる熱射病や重度の日射病といわれる状態)
熱中症になりやすい環境、なりやすいタイプってある?
それでは、熱中症になりやすい環境やタイプはあるのでしょうか。熱中症を起こす要因には「環境」「タイプ(カラダ)」「行動」の3つが考えられています。
- 熱中症になりやすい「環境」(環境要因)
気温が高い、湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、締め切った屋内、エアコンのない部屋、急に暑くなった日、熱波の襲来 など
- 熱中症になりやすい「タイプ」(カラダ要因)
もともとから脱水傾向にある高齢者や乳幼児、一時的な原因で(下痢や風邪、二日酔いなど)脱水傾向にあるとき、糖尿病などの基礎疾患のある人、肥満の人 など
- 熱中症を引き起こしやすい「行動」(行動要因)
激しい筋肉運動や慣れない運動、長時間の屋外作業、水分補給できない状況 など
環境で注意したい点は、気温が低くても湿度が高いと熱中症リスクは高まるということ。室温や湿度の高い屋内での油断は禁物です。さらに「タイプ」では、皮下脂肪が多いほど体内の熱が外に逃れにくくなるため、肥満の人は注意が必要です。
熱中症になりやすいタイプで心配だという人は、熱中症予防を目的として提案された国際的規格の「WBGT(暑さ指数)」をチェックしてみましょう。カラダに影響する湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標で、日常生活やスポーツなどを安全に行なえる目安がわかります。
関連記事:熱中症対策には「WBGT(暑さ指数)」も重要に。日本スポーツ協会、6年ぶりに「熱中症予防ガイドブック」改訂
次:筋肉量アップが予防対策になる?