
子どもの心の成長を妨げる「親のNG言動」とは?愛情不足のまま育った場合、こんな悪影響も (1/3)
子どもの心の成長を支えたい。そう願って日々接している中で、つい何気なくとってしまう言動が、実は子どもの心にブレーキをかけていることがあります。
知らず知らずのうちに自信を失わせたり、感情を押し殺させたり。
本記事では、子どもの健やかな心の発達を妨げる“親のNG言動”をわかりやすく解説します。子どもの可能性を引き出すために、まずは親として気をつけたいこととは?
監修は、プロ野球選手やボートレーサーなどアスリートのパーソナルサポートを行う、株式会社脳レボ代表の川谷潤太さんのもと解説していきます。
後半では、親の愛情を感じることができないまま成長してしまった場合、どんな影響が出てしまうのかについて、各専門家の意見をまとめています。
<このページの内容>
子どもの心の発達に深くかかわる「EQ(心の知能指数)」とは
子どもの心の発達は、感情のコントロールや人間関係などに大きな影響を与えます。非認知能力のひとつで心の知能指数とも言われる「EQ」は、子どもの将来の社会適応力や自己肯定感に深く関わっています。
EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは、感情を理解し、コントロールしながら適切に他者と関わる力を示す指標です。
1995年にアメリカの心理学者ダニエル・ゴールマンが著書『Emotional Intelligence』で提唱したことで広まりました。

IQ(知能指数)が論理的思考力や問題解決力を示すのに対し、EQは人間関係や自己管理能力など、社会性や感情面での適応力を示します。
EQが高い人は、自分の感情をうまくコントロールし、他者との良好な関係を築くのが得意です。
「EQ」と「非認知能力」は何が違う?
EQは感情のコントロールやコミュニケーションに直結し、非認知能力は問題解決力や自立心の強化に関わります。EQは対人関係に、非認知能力は生き抜く力に影響を与える点が異なります。
●EQ・・・自分や他人の感情を理解・コントロールし、人間関係を円滑にする能力。主に自己認識・感情の管理・共感力・社会的スキルなどが含まれます
●非認知能力・・・自己肯定感・忍耐力・好奇心・協調性など、数値化しにくいスキルを指します
EQは専用のテストで測定可能ですが、非認知能力は行動観察で評価されます。
親の言動が子どものEQに与える影響とは
親の言動は子どものEQに非常に大きな影響を与えます。
EQの基礎は幼少期に親との関わりの中で育まれるため、親の態度や接し方がEQの発達に直結します。
たとえば、親が子どもの感情を受け止め、共感しながら対応すると、子どもは「自分の感情を理解してもらえた」と感じて安心し、EQが高まりやすくなります。
一方で、親が子どもの感情を無視したり、否定的な言葉をかけ続けると、子どもは自分の感情をうまくコントロールできず、EQの発達が妨げられます。
子どもの心の成長を遮ってしまう、親のNG言動とは
以下のような親の言動は、子どものEQを低下させる原因となります。
「泣くな!」「悲しむな」など感情を否定する
例:「そんなことで泣くな!」「男のくせに泣くなんて情けない」
子どもが泣いているときに感情を否定されると、「自分の感情は受け入れられない」と感じてしまいます。結果的に自分の感情を抑え込むようになり、感情のコントロールが難しくなります。
OK例:「悲しいんだね。つらかったね」と受け止める
「ダメ」「やめなさい」「意味ない」などと頭ごなしに否定する
例:「そんなことやっても意味ない」「また失敗するよ」
失敗や挑戦を頭ごなしに否定されると、子どもは「自分の選択に意味はない」「自分はダメな人間だ」と感じやすくなります。自己肯定感が低下し、チャレンジ精神が育ちません。
OK例:「どうしたらうまくいくか一緒に考えよう」「○○した理由を教えてくれる?」
「なんでこんなこともできないの?」と比較・否定する
例:「お兄ちゃんはできてるのに、どうしてあなたはできないの?」「こんなこともできないの、皆できてるよ」
他人と比較されると、自己肯定感が下がり、自分への自信を失いやすくなります。他人の目を過度に気にするようになり、ストレス耐性が弱まります。
OK例:「前より上手になったね」「頑張ったね」
「うるさい」「後で」と子どもの話を無視する
例:「後にして」「忙しいから黙ってて」

子どもの話を無視されると、「自分の存在は重要ではない」と感じやすくなります。他人とのコミュニケーションでも「どうせ話しても無駄」と感じ、会話を避けるようになります。
OK例:「今は少し忙しいから、〇〇が終わったらちゃんと聞くね」
「○○してくれたらいい子」など、条件付きの愛情を与える
例:「テストで100点取ったらおもちゃを買ってあげる」「○○しないと嫌いになるよ」
「結果を出さないと愛されない」と感じると、子どもは自分の感情より「他人からの評価」に過剰に依存し、自分の価値を見失います。
OK例:「結果に関係なく、あなたが頑張ったことを素敵だと思ってるよ」
EQが低いと子どもにどんな弊害が出る?
EQが低い子どもは、感情の管理が苦手で、ストレスや不安を感じやすく、人間関係においてトラブルを引き起こしやすい傾向があります。
1. 人間関係でトラブルが増える
• 友達との関係で衝突が増えやすくなる
• コミュニケーションが苦手で孤立しやすい
2. 感情のコントロールが難しくなる
• 怒りや悲しみをうまく処理できず、キレやすくなる
• ストレスに対処できず、精神的に不安定になる
3. 学習や集中力に影響が出る
• 感情の乱れが集中力を妨げる
• 失敗を引きずりやすく、自己肯定感が低下する
4. 自己肯定感や自己効力感が低下する
• 何をやっても「どうせダメだ」と感じやすくなる
• 挑戦を避け、消極的になる
EQが高い子どもの特徴とは
EQ(心の知能指数)が高い子どもは、感情を理解し、適切にコントロールしながら他者と良好な関係を築ける力を持っています。以下のような特徴が見られることが多いです。
自分の感情を理解し、コントロールできる
• 嫌なことがあっても感情的になりすぎず、冷静に対応できる
• 「今、自分は怒っている」「悲しいと感じている」など、自分の感情を言語化できる
• イライラしたときに深呼吸をしたり、気持ちを落ち着ける方法を知っている
例:
「友達に嫌なことを言われてムカッとしたけど、深呼吸してから気持ちを落ち着けて話せた」
「そういうことをされるとイヤだと冷静に伝えられた」

他人の感情を理解し、共感できる
• 友達が悲しんでいるときに「つらかったね」と声をかけたり、寄り添える
• 表情や態度から相手の感情を察し、適切な反応ができる
• 友達が困っているときに助けたり、励ましたりできる
例:
「友達が遊びに誘ってもらえなくて落ち込んでいるのを見て、一緒に遊ぼうと声をかけた」
「仲のいい友達から相談され、相手が落ち着くまで話を聞いた」
自己肯定感が高く、自信を持っている
• 失敗しても「自分にはできる」と前向きに考えられる
• 他人と比較せず、自分自身を大切にできる
• 自分の意見を自信を持って伝えられる
例:
「テストで間違えたけど、次にどうすればいいかを考えて、また頑張ろうと思えた」
「SNSでいいねをもらえなかったけれど、自分がいいと思うので満足」
他者とのコミュニケーションが円滑
• 人の話をしっかり聞き、相手の意見を尊重できる
• 話し合いで意見が合わなくても感情的にならず、冷静に対話できる
• 友達とトラブルが起きたときに落ち着いて解決できる
例:
「友達とおもちゃの取り合いになったけど、話し合って順番に使うことにした」
「意見が違う相手の価値観を否定せず、聞いた後、落ち着いて自分の意見を伝えた」

ストレス耐性が高く、深く落ち込みにくい
• 嫌なことや失敗があっても、気持ちを切り替えやすい
• ストレスを感じたときに、自分なりの解消法を持っている
• 必要なときには親や友達に相談できる
例:
「部活の試合で負けたけれど、悔しい気持ちをバネにして次の練習を頑張ろうと思えた」
「親と喧嘩をしたが、気分転換をして関係性を修復できた」
問題解決能力が高い
• トラブルが起きたときに、感情に流されず冷静に対応できる
• 自分で解決できないときは親や先生に相談できる
• 感情に振り回されず、適切な行動が取れる
例:「いじめを受けたが、限界になる前に周りの大人に相談した」
EQが高いと人間関係が良くなり、ストレスへの対応力や自己肯定感も高まるため、社会生活や仕事でも大きな強みとなります。
もっともEQを下げてしまうNG行為は?
今回はEQ(心の知能指数)を下げてしまう「親のNG言動」について、具体例を用いながらご紹介いたしましたが、何よりもっともEQを下げてしまうNGな行為は「無視」です。
たとえば、声をかけてもらえない、話を聞いてもらえないなど、子どもに孤独を感じさせてしまうことが一番よくありません。
ですからまずは、ちょっとした声かけや会話を増やして、できる限り最後まで話を聞いてあげることです。
仕事に追われてなかなか子どもとの時間を過ごすことができない場合は、手紙にして想いを伝えるなど、少しでも子どもが親からの愛を感じられるように工夫してみましょう。
おはよう、ありがとう、おやすみのような、日常的な挨拶も大切です。もちろん笑顔で!
監修者プロフィール
株式会社脳レボ代表
川谷潤太(かわたに じゅんた)
兵庫県の大手学習塾において、当時最年少で校⻑に就任後、1教室で1,000名以上の生徒が通う学習塾に発展させ、講師研修や入試特番テレビのコメンテーターなども務める。その後、岡山県の創志学園高校へ赴任し、学校改革とスポーツメンタル指導を担当。史上最速、創設1年、全員1年生で甲子園に出場した硬式野球部では3季連続甲子園出場を果たし、6名のプロ野球選手が誕生。ソフトボール部では3季連続日本一、柔道部では日本一や世界一の選手も輩出した。
2019年に株式会社 脳レボを創設し、オリンピック選手やプロ野球選手など、アスリートやスポーツチームへのメンタル指導、子ども‧保護者‧教員向けの教育講演、企業の人材育成マネジメントや研修などを手がけ、講演回数は8年間で1,500回以上、受講者は12万名を突破。脳科学や大脳生理学、バイオフィードバック工学をベースとした、具体的かつ実践的な手法により、多くの方の願望目標達成をサポートしている。
株式会社脳レボ
https://nourevo.co.jp/
子どもの心の成長は、親の言動が大きく影響することをお届けしました。ここからは、親の愛情を感じることができないまま成長してしまった場合、どんな影響が出てしまうのかについて。
各分野の専門家の意見をまとめ、愛情不足で育った大人に共通する傾向をお届けします。
親子関係心理学の専門家が語る、愛情不足で育った大人の特徴とは
監修者プロフィール
親子関係心理学の専門家・合同会社serendipity
三凛さとし
夢を追って渡米したものの借金苦と活動の失敗によりホームレス寸前の生活に。「何かおかしい」と感じ、心理学や自己啓発を勉強する中で、人生を好転させる方法を習得。お金、時間、場所、人間関係、心身の健康(人生の5大自由)を実現するということをテーマに2014年より各SNSにて情報発信。2022年にはKADOKAWAより親子関係心理学についての書籍「親子の法則」を出版し、発行部数6万部を記録。2024年9月にはメンタルからお金の問題を解消する「金のなる本 誰でも再現できる一生お金に困らない方法」を発売。ABEMA TV -For Japan- 日本を経営せよ!、テレ玉「BOSSのプレゼン」など、メディア出演多数。
親から十分な愛情を受けずに育った人には、おもに以下の特徴が見られることが多いようです。
多くの面において自己肯定感が低い
自分を価値ある存在として認識するのが難しいため、自信を持てない、自分を過小評価しがちです。
対人関係が不安定になりやすい
愛情を受けた経験が多くないため、他者との親密な関係を築くことが苦手で、依存的になったり逆に距離を取り過ぎたりします。
感情のコントロールが苦手である
感情のコントロールが苦手で、ストレスや不安に対して過敏に反応する、過度に喜ぶなど感情的になりやすいです。
愛情不足で育ってきた人は、どんな思考の偏りが生まれやすい?
上記のような愛情不足の環境で育つと、以下のような思考の偏りが生じやすくなります。
「他人の評価がすべて」
親からの肯定を得られなかったことで、他者の評価に依存しがちで、自分自身の評価基準を持つのが難しくなります。
人は多少なりとも他者の評価で生きている部分はありますが、愛情不足で育った人は、大部分を他者評価に委ねてしまいがちです。
「自分は愛される価値がない」
幼少期に愛されなかったという経験から、自分は愛されるに値しない存在だと思い込み、「どうせダメ」など自らの可能性を制限することが多いです。
「完璧でなければならない」
他人に認められるために、自分を完璧であるべきだと強く思い込み、失敗や不完全さを極端に恐れる傾向があります。
愛情不足で育ってきた人が悩みやすい問題行動
必ずしもすべての人に当てはまるわけではありませんが、愛情不足の影響が深い場合、以下のような傾向が現れやすいです。
対人関係における問題
愛情不足で育つと、他者との絆や信頼感を築くのが難しくなりやすいと言われています。過度な依存や試し行為、頻繫な人間関係リセットなどが見られることも。
反対に、親からの無条件の愛情を受け取れなかった経験が原因で、人との深い関わりを避ける「回避的な態度」が形成されることもあります。
他人に心を開くことを恐れ、孤立を選ぶ場合が多く、結果的に孤独感が増してしまいます。
感情コントロールが苦手
子どもの頃に親から感情を否定された、無視された経験があると、感情を健全に表現する方法を学べないことがあります。
怒りや悲しみ、不安などの感情を適切に表現できず、ストレスが溜まりやすくなります。爆発的な怒りや、逆に感情を抑え込み過ぎて無気力になることも。
感情を長期間にわたって抑え込むことで、ある時点で感情が爆発することもあります。些細なことで激怒したり、過剰に悲観的になったりするなど、感情のコントロールが効かなくなる場合があります。
自己肯定感が低く、挑戦できない
愛情不足で育った人は、自分の価値を他者からの評価に依存しがちです。
親からの無条件の愛情を経験していないため、「自分は愛されるに値しない」「どうせダメ」と感じることが多く、自己肯定感が低くなる傾向があります。これにより、チャレンジ精神の欠如や失敗への恐怖として現れることがあります。
依存気味、相手をコントロールしようとする
愛情を求めて他人に過剰に依存する傾向があり、執着やコントロール欲求を持ちやすくなります。恋愛や友情で相手に過剰に期待し、少しの不安や疑念で相手に対する信頼を失うことがあります。
また、自分と他者の境界が曖昧になりがちで、相手の感情や意見を過度に受け入れてしまうか、逆に自分の感情を押し付けることがあります。
反社会的・攻撃的な行動をしてしまう
愛情不足からくるフラストレーションや寂しさが、攻撃的な行動として現れることがあります。
とくに、親や上司といった権威者に対する反抗的な態度や、自己防衛として周囲に対して攻撃的になる傾向が見られることがあります。
アルコールやギャンブル依存症などリスクが高い行動を行う
アルコールや薬物に頼る、過度なギャンブルに走るといったリスクの高い行動を取ることがあります。
これらは、心理的な不安定さや空虚感を埋めようとする自己破壊的な行動の一環です。
完璧主義や過度な自己批判
条件つきの愛情しか与えられなかった場合、完璧でない自分を許せないという思考パターンが形成されることがあります。
常に「もっと努力しなければ」「自分はまだ不十分だ」と考え、失敗やミスに対して過剰に自分を責める傾向があります。
親や他者の期待を満たそうとする完璧主義思考により、心身に大きな負担がかかこともあります。
不安障害や人格障害、うつ病のリスク
愛されなかった経験が「自分は価値がない」という根本的な感覚を植え付けてしまい、それによる問題行動や課題により不安障害や人格障害、うつ病といったリスクが高まることがあります。
次:臨床心理士が語る、愛情不足で育った大人の特徴とは


 子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法
子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法 「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは
「子どものため」が「虐待」に。小児科医が警鐘を鳴らす「教育虐待」とは 辛い時、「悩みを相談できる人」がいない。誰かに話を聞いてほしい…どう切り抜ける?
辛い時、「悩みを相談できる人」がいない。誰かに話を聞いてほしい…どう切り抜ける?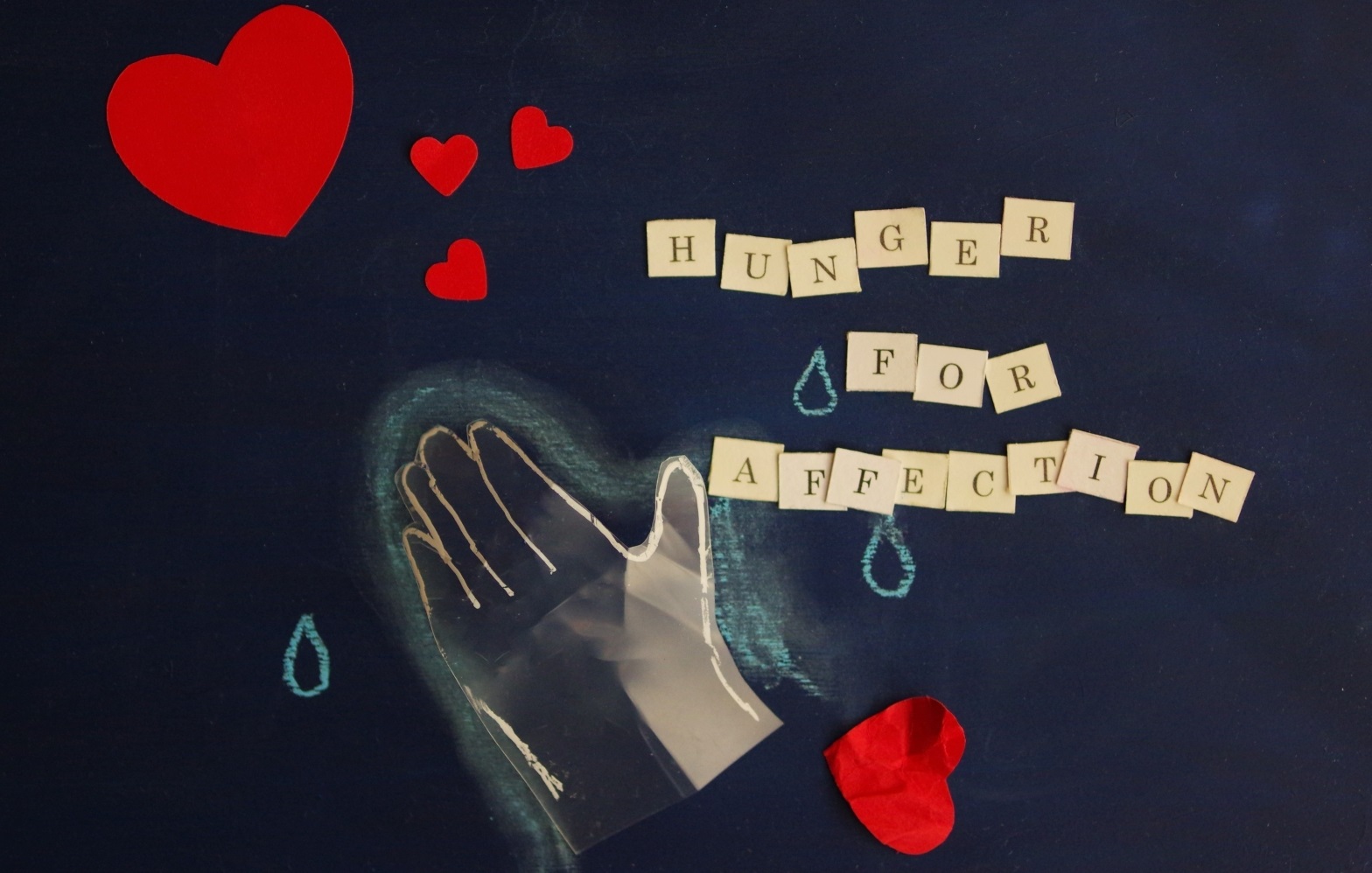 愛情不足で育ってきても、問題なく成長している人もいる。その理由とは
愛情不足で育ってきても、問題なく成長している人もいる。その理由とは







