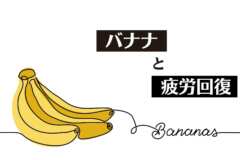疲労回復に一番効くのは睡眠!栄養・運動・昼寝でも回復力UP
疲れが取れない…眠い…。疲労回復に一番効果的なのは何ですか?
答えてくれたのは、脳神経外科医・医学博士、SOグレイスクリニック院長・近藤 惣一郎先生。
「医学的に最も疲労回復に効果があるのは、体と脳を同時に休ませる『質の高い睡眠』です。睡眠中に成長ホルモンが分泌され、脳や体の細胞が修復されると同時に、自律神経や免疫も整うからです。質の高い睡眠こそが、心身を立て直す最も確実な方法です」
では、質の高い睡眠をとるために何ができるのか?その方法と、睡眠以外でできる疲労回復術も教えてもらいました。
<このページの内容>
疲労回復に一番効くのは「質の高い睡眠」
人は睡眠中に成長ホルモンが分泌され、脳や筋肉、内臓など全身の細胞が修復されます。さらに自律神経のバランスが整い、免疫機能も回復するため、翌日の集中力や体力へとつながります。
質の高い睡眠には、まず、寝室環境を整えることが大切です。強い光を避け、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控えることで、睡眠の深さが変わります。また、寝る前にストレッチや入浴をすることで、副交感神経が優位になり、深い眠りへと導いてくれます。
睡眠以外では、疲労回復に効果的な食べ物やアクティブレスト、短時間の昼寝などで直接疲労を和らげられます。これらを組み合わせることで、心身を効率よく回復させることができます。
睡眠の質を高める方法1:入浴
入浴は、心身をリラックスさせて深い眠りに導きます。温度や入り方を工夫することで、より効果的に疲労を和らげられます。
ぬるめのお湯で副交感神経を優位にする
就寝前に38〜40度ほどのぬるめのお湯に浸かると、副交感神経が優位になり、心身が落ち着いて入眠しやすくなります。体温が一度上がってから下がる過程で眠気が訪れるため、就寝の1時間前に入浴を終えるのが理想です。お気に入りの入浴剤を加えれば、香りによるリラックス効果も期待できます。
睡眠の質を高める方法2:ストレッチ
寝る前の軽いストレッチは、体の緊張をほぐし、自律神経を整えて入眠をスムーズにします。快眠をサポートする習慣として取り入れましょう。
自律神経を整える、寝る前のストレッチ
疲れているのに眠れないときは、体が緊張したままになっていることがあります。寝る前にゆっくり筋肉を伸ばすと副交感神経が優位になり、心も体も落ち着いて眠りに入りやすくなります。
\動画で動きをチェック/
\動画で動きをチェック/
\タップして動画を再生/
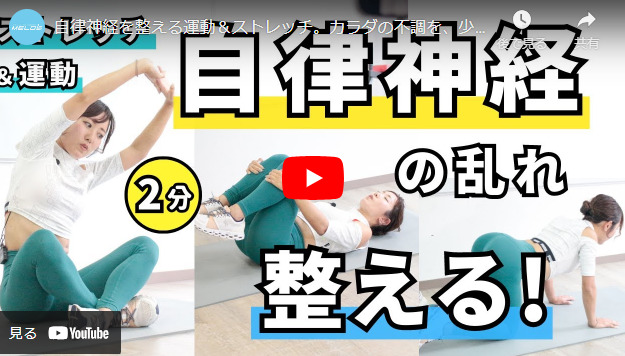 関連記事:【寝つき・疲れ・不安】自律神経を整える簡単ストレッチ3つ(最短5秒~2分)
関連記事:【寝つき・疲れ・不安】自律神経を整える簡単ストレッチ3つ(最短5秒~2分)
デスクワーク疲れに効く、座ったままストレッチ
日中のデスクワークで肩や腰がこわばると血流が滞り、強い疲労感につながります。そのまま布団に入ると、深い眠りに入りにくくなることも。
そこで役立つのが、「座ったままできるストレッチ」です。寝る前に取り入れることで全身がリラックスしやすくなり、スムーズな入眠を促します。
\タップして動画を再生/
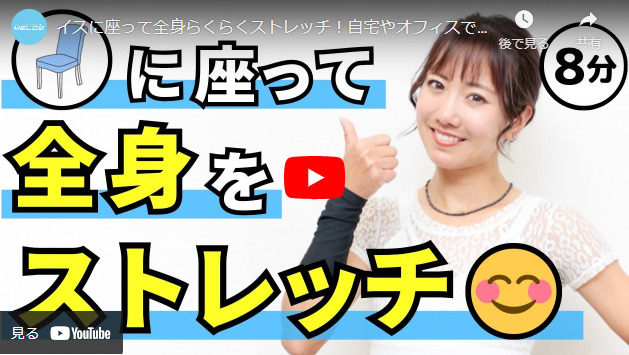
疲労回復法1:疲労回復に効果的な食べ物
疲労の原因によって、疲労回復に効果的な食べ物は異なりますが、栄養素をバランスよく摂ることが基本です。代表的な栄養素と、その働きを紹介しましょう。
糖質でエネルギーを補給
疲労の大きな原因はエネルギー不足です。ご飯やパン、麺類、いも類に含まれる糖質は、体内でブドウ糖となり脳や体を動かすエネルギー源になります。疲労を感じるときは、消化にやさしいおかゆやうどんなどにすると、胃腸への負担も少なくおすすめです。
ビタミンB群で代謝を助ける
ビタミンB群はエネルギー代謝に不可欠です。特にビタミンB1は糖質をエネルギーに変える役割があり、疲労回復に直結します。豚肉や鶏むね肉、うなぎ、マグロ、納豆、卵に豊富に含まれます。玉ねぎやにんにくのアリシンと一緒に摂ると吸収が高まります。
関連記事:猛暑日は「冷やしみそ汁」で疲労回復!医師や管理栄養士もおすすめする理由
クエン酸で乳酸を分解
レモンやみかん、梅干しなどに含まれるクエン酸は、エネルギーを生み出す回路を活性化し、疲労物質である乳酸の蓄積を抑えます。スポーツ後や疲労を感じるときに取り入れると効果的です。
関連記事:はちみつレモン、なぜ疲労回復に効く?管理栄養士が語る4つの理由
タンパク質とアミノ酸で体を修復
筋肉や臓器を修復するにはタンパク質が不可欠です。鶏肉や魚、卵、大豆製品を意識的に取り入れましょう。分解されたアミノ酸は吸収が早く、特にBCAAは筋肉修復を助け、グルタミンは免疫を支えます。サプリや飲料で補助的に摂るのも有効です。
関連記事:必須アミノ酸「BCAA」の効果と飲み方。筋肉の分解を防ぐってホント?
イミダゾールジペプチドで疲労感を軽減
鶏むね肉やカツオ、マグロに含まれるイミダゾールジペプチドは、活性酸素を除去して疲労感を和らげる働きがあります。鶏むね肉は茹でたり蒸したりしただけでもOK。茹で汁をスープに使えばさらに効率的です。カツオやマグロは刺身のように生で食べるのが最も効率的ですが、加熱調理でも十分に補給できます。
鉄分で酸素を運ぶ
鉄分は体中に酸素を運ぶ役割を担い、不足すると疲労や倦怠感の原因になります。レバー、赤身肉、あさり、しじみ、イワシなどをバランスよく食べることが大切です。動物性食品の鉄分(ヘム鉄)は吸収率が高く、ビタミンCと一緒に摂るとさらに効率的。たとえばレバー炒めにレモンを絞ると吸収を助けます。
ビタミンC・Eで酸化ストレスを抑える
ビタミンCやEは抗酸化作用があり、疲労の原因となる活性酸素を抑える働きがあります。ビタミンCは柑橘類やキウイ、イチゴに、ビタミンEはナッツや魚介類、アボカドに多く含まれます。フルーツは生でそのまま、ブロッコリーは軽く蒸すことでビタミンCを逃さず摂取できます。ナッツはおやつ代わりに食べると手軽です。
効果的な食事のポイント
・栄養素に偏らず、バランスよく食べる
・疲れているときはお粥やスープなど消化にやさしい調理法にする
疲労回復法2:アクティブレストで疲労物質を排出
疲れたときはゴロゴロして休みたくなりますが、じっとしているだけでは疲労が抜けにくいことも。体力がある場合は、軽く体を動かす「アクティブレスト」を取り入れると、血流が促進され疲労物質の排出が進み、回復が早まることもあります。
軽い有酸素運動で血流を促す
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、呼吸や循環を活発にし、体内にたまった疲労物質を効率よく排出します。一定のリズムで体を動かすと「セロトニン」が分泌され、気分が安定しやすくなるのもメリットです。
強度を高める必要はなく、会話ができる程度の軽い運動を20〜30分行うだけで十分な効果があります。
疲労回復法3:短時間の昼寝
昼寝は夜の睡眠を補うだけでなく、脳をリフレッシュさせて午後の集中力を高めます。取り入れ方を工夫すれば、疲労回復に大きな効果を発揮します。
30分以内の昼寝で頭と体をリセット
昼寝は長く取りすぎると深い眠りに入ってしまい、起きたときにだるさを感じやすくなります。効果的なのは15〜30分程度の短い昼寝です。この長さなら脳の疲れをリセットでき、午後の作業効率が上がります。
タイミングは午後の早い時間に
昼寝をするなら午後1〜3時がベストです。遅い時間に眠ってしまうと夜の睡眠に影響するため注意が必要です。眠れなくても目を閉じて横になるだけで脳は休まり、リラックス効果を得られます。
疲労回復に関するQ&A
Q. 疲れたときは寝だめやゴロゴロで回復する?
A. 実はあまり効果的ではありません。体を動かさないで休むだけでは血流が滞り、疲労物質の排出が進みません。ウォーキングなどの「アクティブレスト」を取り入れた方が回復が早いとされています。
Q. お風呂に浸かると疲れがとれるって本当?
A. 本当です。ぬるめのお湯に浸かることで副交感神経が優位になり、心身がリラックスして睡眠の質が上がります。血液循環も良くなるため、疲労回復の基本的な習慣としておすすめです。
Q. カフェインは疲労回復を妨げる?
A. 飲んでも構いませんが、作用が4〜5時間続くため夕方以降は控えるのがベターです。眠りを浅くしてしまう可能性があるため、寝つきの悪さを感じている人は特に注意が必要です。
Q. 疲労回復におすすめの食材は?
A. バナナがおすすめです。バナナに含まれるトリプトファンは「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンを作り、さらに睡眠を促すメラトニンの分泌にもつながります。朝食に取り入れると1日のリズムも整いやすくなります。
監修者プロフィール
美容外科 SO グレイスクリニック院長
近藤惣一郎
 医学博士(京都大学)
医学博士(京都大学)
ロンリー侍ドクター
日本脳神経外科学会専門医
日本美容外科学会(JSAS)専門医
1988年 京大医学部卒
若返り専門の美容外科医。美は健康の上になり立つという理念のもと、正しい食生活・運動習慣・ダイエットに関する知識が豊富で、自らもダンサーとして、プロフィッシングアングラー(DAIWA)として、若さとナイスボディを保ち続ける。
Instagram:https://www.instagram.com/kondo.soichiro/

 お風呂に入れば睡眠の質も上がる。疲れたカラダに効果的な入浴法をお風呂博士に聞いてみた(前編)
お風呂に入れば睡眠の質も上がる。疲れたカラダに効果的な入浴法をお風呂博士に聞いてみた(前編)

 体の疲れをとる「アクティブレスト」のメニューとやり方
体の疲れをとる「アクティブレスト」のメニューとやり方 睡眠の質が向上する「朝食の食材」ランキング!1位は「バナナ」、その理由は
睡眠の質が向上する「朝食の食材」ランキング!1位は「バナナ」、その理由は