
「働いてるだけなのに、なんでこんなにしんどい?」心を病みやすい職場の特徴とは (3/3)
「ありがとう」「助かったよ」「おはよう」「お疲れ」など、感謝や承認の言葉を積極的に伝える
こうした言葉は相手の存在や行動を認めるサインになります。
人は「自分はここにいていい」「自分の行動が誰かの役に立った」と感じることで、自己肯定感やモチベーションが高まり、安心して行動できるようになります。
また、感謝が飛び交う職場は信頼関係が築かれやすく、心理的安全性が自然と育まれていきます。些細な一言でも、チーム全体の空気をポジティブに変える力があります。
失敗やミスを責めない
ミスや失敗は、条件が揃えばだれにでも起きるものと捉えます。個人が悪いのではなく状況や仕組みに問題があるとして、原因と改善点を話し合いましょう。
それにより安心して挑戦できる環境となり、心の安定だけでなく業務パフォーマンスアップにもつながります。
立場や役職に関係なく意見を言える場をつくる
上下関係に関わらず、誰でも発言できる仕組みが必要です。上司の目線だけでも、部下の目線だけでもよくありません。
具体的には、定期的な1on1ミーティングや雑談タイムを設けるなどがあります。たとえ解決しなくても、意見を聞いてもらえる職場であるという認識が、会社への信頼度を高めます。
ハラスメントが放置されていないか、定期的に啓蒙活動を行う
ハラスメント対策を徹底することも欠かせません。ハラスメントが許容されている職場では、それが“当たり前”になってしまうリスクがあります。
本当は嫌だと感じているにもかかわらず「誰も注意しない」「上司がやっている」「声を上げても握りつぶされる」といった空気があると、職場全体が“ハラスメント容認文化”に染まってしまいます。

「朱に交われば赤くなる」といいますが、こうした社風だと、やがてハラスメントをしていなかった人まで「あれくらいの強い言葉を使っていいんだ」「机を叩くくらいはしょうがない」「怒鳴るのも仕方ない」と、どんどん感覚がおかしくなっていくことも。
最初の一件を「見逃さない」「放置しない」こと。見逃しが続くと、健全な人間関係や心理的安全性がどんどん失われていきます。
自分を守るには、他者ではなく「自分の感覚」を信じること
メンタルを病みやすい職場で自分を守るためには、まず「これはおかしい」と感じた自分の感覚を信じることが大切です。
一人で抱え込まず、信頼できる人や社外の相談窓口に早めに相談を。証拠(日付や内容のメモ、録音)を残しておくことも、自分を守る手段になります。
社内で改善が見込めない場合は、異動や転職も視野に入れてOK。自分の心と身体の安全を最優先に考えましょう。
監修者プロフィール
神谷町カリスメンタルクリニック院長
松澤 美愛先生
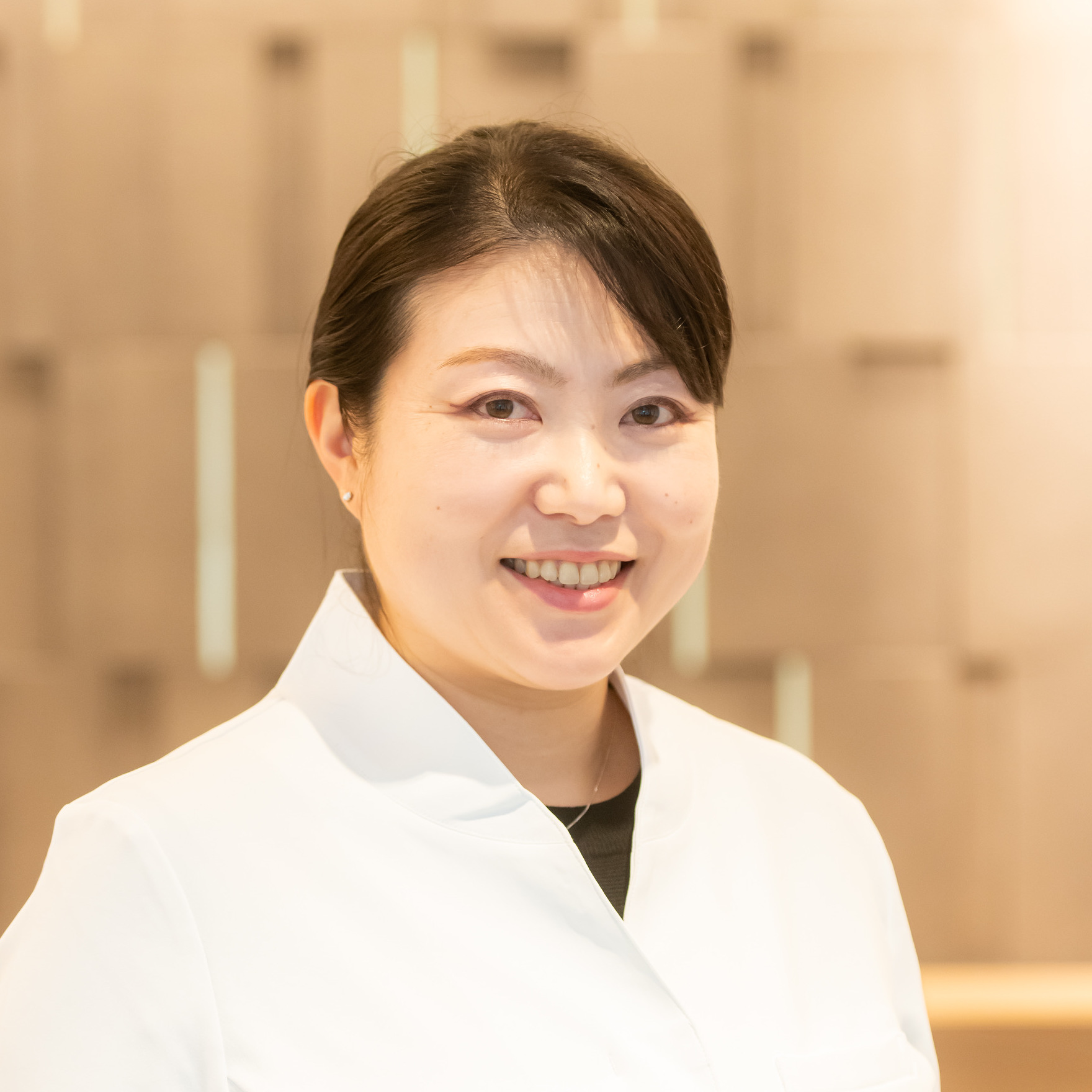 東京都出身。慶應義塾大学病院初期研修後、同病院精神・神経科に入局。精神科専門病院での外来・入院や救急、総合病院での外来やリエゾンなどを担当。国立病院、クリニック、障害者施設、企業なども含め形態も地域も様々なところで幅広く研修を積む。2024年東京都港区虎ノ門に「神谷町カリスメンタルクリニック」を開業、院長。精神保健指定医/日本精神神経学会/日本ポジティブサイコロジー医学会
東京都出身。慶應義塾大学病院初期研修後、同病院精神・神経科に入局。精神科専門病院での外来・入院や救急、総合病院での外来やリエゾンなどを担当。国立病院、クリニック、障害者施設、企業なども含め形態も地域も様々なところで幅広く研修を積む。2024年東京都港区虎ノ門に「神谷町カリスメンタルクリニック」を開業、院長。精神保健指定医/日本精神神経学会/日本ポジティブサイコロジー医学会
URL https://charis-mental.com/
InstagramURL https://www.instagram.com/charismentalclinic
<Edit:編集部>

 辛い時、「悩みを相談できる人」がいない。誰かに話を聞いてほしい…どう切り抜ける?
辛い時、「悩みを相談できる人」がいない。誰かに話を聞いてほしい…どう切り抜ける?





