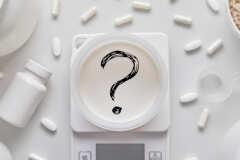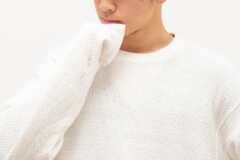「過保護 or 放任で育った大人」に多い“性格の特徴”とは
「親に構われすぎた」「逆に放っておかれた」――そんな子ども時代を過ごした人は、大人になってからも人間関係や自己評価に独特のクセが出ることがあります。
過保護と放任、どちらの育ち方も一長一短。今回は、それぞれの家庭で育った大人に見られやすい“性格の特徴”や傾向について、専門家の意見を見ていきましょう。
まずは過保護なパターンから。
母親から過干渉されて育った人は、大人になってどんな影響が出やすい?
過保護すぎる環境で育つと、その影響は子ども時代だけで終わらず、大人になってからも人間関係や自己肯定感、意思決定のあり方に色濃く残ることがあります。
母親の過干渉は、大人になった私たちにどんな影響を与えるのか。また、大人になってからも過干渉されている場合、どう対処するとよいのでしょうか。神谷町カリスメンタルクリニック院長の松澤美愛先生監修のもと、見ていきましょう。
監修者プロフィール
神谷町カリスメンタルクリニック院長
松澤 美愛先生
東京都出身。慶應義塾大学病院初期研修後、同病院精神・神経科に入局。精神科専門病院での外来・入院や救急、総合病院での外来やリエゾンなどを担当。国立病院、クリニック、障害者施設、企業なども含め形態も地域も様々なところで幅広く研修を積む。2024年東京都港区虎ノ門に「神谷町カリスメンタルクリニック」を開業、院長。精神保健指定医/日本精神神経学会/日本ポジティブサイコロジー医学会
URL https://charis-mental.com/
InstagramURL https://www.instagram.com/charismentalclinic
どんな行動が「過干渉」にあたるのか?
「過干渉」とは、子どもが自分で考えたり選んだりする機会を奪い、親が必要以上に介入してしまうことを指します。具体的な行動の例としては、次のようなものがあります。
- 子どもの持ち物や服装、勉強方法まで親が細かく決めてしまう
- 子どもが失敗する前に先回りして口を出し、体験のチャンスを奪う
- 子どもの交友関係に過度に口を出し、会う相手や遊び方を制限する
- 子どもの意見よりも「親の考えが正しい」と押しつける
- 本人が望んでいない習い事や進路を強く勧める、または強制する
こうした行動は「子どものため」という気持ちから出ることも多いですが、度が過ぎると子どもの自主性や自己肯定感を育みにくくし、将来の人間関係や意思決定にも影響を及ぼす可能性があります。
母親から過干渉されて育った場合、成長するとどんな影響が出やすい?
母親から過干渉されて育つと、成長後の性格や人間関係にさまざまな影響が表れやすくなります。
自分で決断するのが苦手
まず多いのは、自分で決断するのが苦手になることです。
子ども時代に親が何でも決めてしまうと、自分で考えて選ぶ経験が不足し、大人になっても「どちらを選べばいいかわからない」「間違えたらどうしよう」と不安になりやすくなります。
自己肯定感が低い
また、自己肯定感の低さも目立ちます。常に「親に認められるかどうか」が基準だったため、自分の価値を自分で感じにくくなり、「どうせ自分なんて」と思い込みやすい傾向があります。
人間関係の距離感が掴みにくい
さらに、人間関係で相手に依存したり、逆に距離をとりすぎたりするケースもあります。
誰かに強く影響されるのが当たり前になっていた人は相手に依存しやすく、逆に「もう二度と干渉されたくない」という気持ちから、人と距離を置きすぎることもあります。
そのほか、完璧主義や強い劣等感、失敗を極端に恐れるなども過干渉の影響としてよく見られます。母親の過干渉は「自分で考えて行動する力」と「自分を肯定する力」を育ちにくくする可能性があると言えます。
なぜ父親より「母親」が過干渉になりやすいのか?
父親よりも母親のほうが「過干渉」と指摘されやすいのには、いくつかの背景があります。
まず、日本を含む多くの家庭では、子どもと一緒に過ごす時間が母親のほうが長い傾向があります。毎日の生活習慣や勉強、友達関係など細かい場面に関わる機会が多いため、自然と口を出す回数も増えてしまうのです。

さらに、母親は「子どもを守りたい」「失敗させたくない」という保護本能が強く働きやすいとも言われています。その気持ちは愛情の裏返しですが、度が過ぎると子どもの選択や行動に介入しすぎてしまい、過干渉につながります。
文化的な要因も無視できません。日本の家庭文化では「母親=子育ての中心」というイメージがいまだ強く、しっかり育てなければというプレッシャーが母親に集中します。その結果、子どもの行動を細かく管理しがちになりまです。
ほか、過干渉になりやすい母親にはいくつか傾向がみられます。
- 心配性で「失敗させたくない」と強く思う母親
- 「自分の考えが正しい」と思い込みやすい母親
- 自分自身が不安定で、子どもに依存してしまう母親
- 世間体を気にしすぎる母親
父親からの過干渉もある
母親ほど注目されにくいですが、父親からの過干渉も存在します。
父親の過干渉は、母親のそれと少し性質が異なることが多く、進路や学業、仕事の選択への強い介入として現れることがあります。たとえば「この大学に行け」「この職業に就け」「もっと稼げるようになれ」といった形で、子どもの将来設計を親の価値観で強くコントロールするケースです。

また、スポーツや習い事への口出しも典型です。「もっとこう練習しろ」「試合で失敗するな」といった強い干渉は、子どもの自主性を奪い、プレッシャーや萎縮につながることがあります。
父親が「家族を導く存在」としての責任感を強く持つあまり、無意識に過干渉になってしまうことが多いのです。その結果、子どもは「自分で選ぶ力」が育ちにくくなり、父親の顔色を気にして行動するようになってしまいます。
つまり、父親からの過干渉も確かにあり、その影響は母親のケースと同じように、大人になってからの自己肯定感や意思決定のスタイルに影響を与える可能性があります。
親に放置されて育った大人に共通する特徴とは
逆に、構われない状態が長く続いた場合、どのような影響が出てきやすいでしょうか。
ここからは、子どもの成長発達にくわしい臨床心理士、公認心理師で一般社団法人マミリア代表理事の鎌田怜那さん監修です。
監修者プロフィール
臨床心理士 鎌田怜那(かまだ・れいな)
一般社団法人マミリア代表理事。臨床心理士、公認心理師。
【所属学会・協会】
・日本臨床心理士会
・日本公認心理師協会
・日本心理臨床学会
・日本アタッチメント育児協会
公式サイト https://mamilia.jp/
「親に放置されて育つ」ってどういうこと?
放置されて育ったとは「ネグレクト(養育放棄)」とも呼ばれ、食事や衣服などの物理的な世話だけでなく、愛情や会話、安心感を十分に与えられない状態も指します。
簡単にいうと、子どもに必要な関わりや愛情が十分に与えられない状態で育つことです。
- ご飯を与えない、服を用意しない、病院に連れていかないなど、身体的なお世話をしない
- 話を聞いてもらえない、抱きしめてもらえない、褒めてもらえないなど、心理的な関わりが乏しい
- 子どもが困っていても助けない、危険から守らないなど、安心感が育ちにくい など

「放置」と聞くと、深刻な虐待のイメージを思い浮かべる人もいるかもしれませんが、もっと軽い形でも起こりえます。たとえば以下など。
- 親が忙しくてほとんど会話をしてくれなかった
- 勉強や運動には厳しいのに、気持ちのサポートはしてもらえなかった
- 家族の中で居場所がなかった
こうした経験も「放置された」と感じる要因になることがあります。
放置されて育った子どもが抱えやすいものとは
子ども時代に「親から十分に関わってもらえなかった」と感じている人は、意外と少なくありません。
食事や衣服などの最低限の世話はされていても、気持ちを受け止めてもらえなかったり、安心できる言葉をかけてもらえなかったり。こうした「放置された」経験は、大人になってからも性格や人間関係に影響を与えることがあります。
では、どんな特徴が表れやすいのでしょうか? ここでは代表的なものを紹介します。
自己肯定感が低くなりやすい
「自分は大切にされない存在だ」と子ども時代に感じてしまうと、そのまま大人になっても「どうせ自分なんて」という思考が抜けにくくなります。挑戦や人間関係において、自信を持ちにくい傾向が見られることがあります。
人との距離感が不安定になりやすい
放置された経験から、対人関係での距離の取り方が極端になりがちです。相手に依存して過剰にしがみついてしまうケースもあれば、逆に「どうせ無駄」と思って他人を突き放してしまうこともあります。
承認欲求が強くなる傾向
「誰かに認めてもらいたい」「愛されたい」という気持ちが強まり、大人になってから過度に他人の評価を求めることがあります。
SNSに異常にのめり込みやすいのも、この傾向が示唆されています。
感情コントロールが難しい傾向
小さい頃に気持ちを受け止めてもらえなかったため、自分の怒りや不安をどう表現していいのか分からない人もいます。
結果として、感情を溜め込みすぎたり、突然爆発してしまったりすることがあります。
恋愛やパートナーシップでの課題
愛情のやりとりに自信が持てず、「嫌われるのでは」と不安を抱えやすい傾向があります。逆に、愛情をうまく表現できず、距離が生まれてしまうことも。
恋愛や結婚において「安心感を得にくい」と感じやすいのが特徴です。
「存在を認めて貰えていない」と感じてしまう――深刻なケースに見られる影響
子ども時代に親から極端に放置され、「そこにいても誰にも気にかけてもらえない」という経験を重ねると、自己肯定感の低さを超えて、「自分は存在する意味がない」と感じてしまうほど深刻な影響が残ることがあります。
こうした人は、大人になっても「生きている実感」や「喜び」を感じにくく、どこか浮いているような感覚(浮遊感)を抱えて日々を過ごしていることがあります。感情が麻痺したようになり、怒りや悲しみ、喜びすら感じにくい。何かをしても虚しさが残るといった状態です。
また、目標や人生の目的を見出せず、慢性的な無気力感や抑うつ状態に苦しむケースも見られます。他者との共感が難しくなり、孤立を深めてしまうこともあるでしょう。
男女で差はある? こんな傾向の違いが現れやすい
大人になって現れるこうした問題。男女で特徴に差はあるのでしょうか。
男性は「一人で完結」傾向に
放置された経験を持つ男性は、他者との関係性に価値を見出しにくくなる傾向があります。何かあっても「人に頼る」という発想がそもそもなく、自分の内側ですべて処理しようとすることが多いのです。
まるで“一匹狼”のように、感情や悩みを他者と分かち合う機会がほとんどない状態になっている場合もあります。他者とのつながりを避けるぶん「自分の正しさだけ」を拠り所にしやすく、対話や協調が苦手になりやすい面もあります。
単なる「感情表現の苦手さ」にとどまらず、幼少期の放置によって人への信頼や共感を育てる土台が築けなかったことが背景にあると考えられます。
女性は「依存気味、他者優先」に
一方で女性は、パートナーからの愛情を強く求める傾向が出やすいと言われます。
小さい頃に満たされなかった愛情を埋めるように、恋人や夫に依存しすぎてしまったり、「嫌われたらどうしよう」という不安を抱えてしまったり。
結果として、自分の意見を抑え込み、相手を優先してしまう人も少なくありません。
<Edit:編集部>

 幼少期、「親に甘えられなかった人」にはどんな特徴がある?大人になってからこんな“反動”も
幼少期、「親に甘えられなかった人」にはどんな特徴がある?大人になってからこんな“反動”も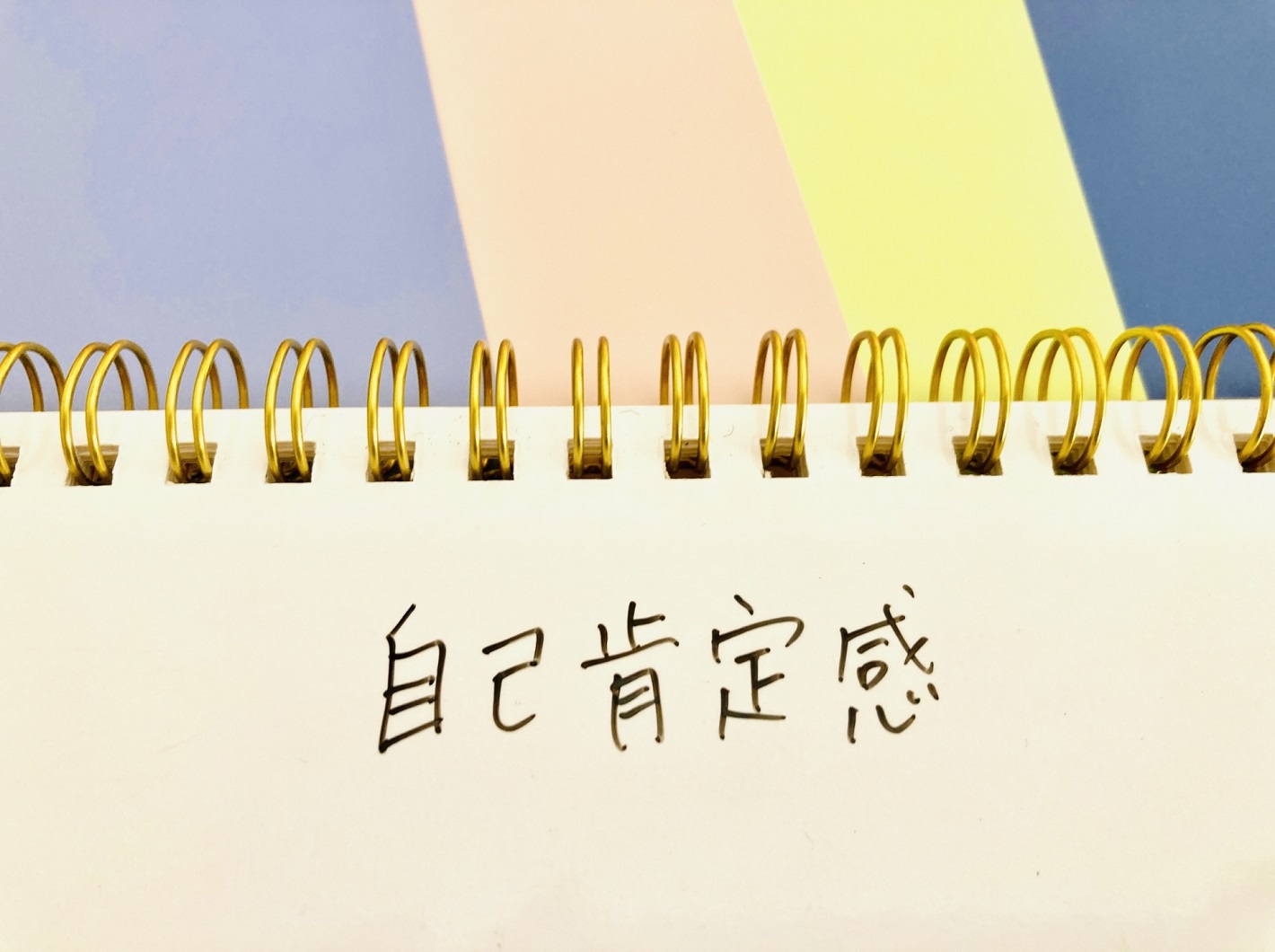 「自己肯定感が高い人は、他者も自分も大切にできる人」。心理専門家が考える、自己肯定感が高い人・低い人とは
「自己肯定感が高い人は、他者も自分も大切にできる人」。心理専門家が考える、自己肯定感が高い人・低い人とは