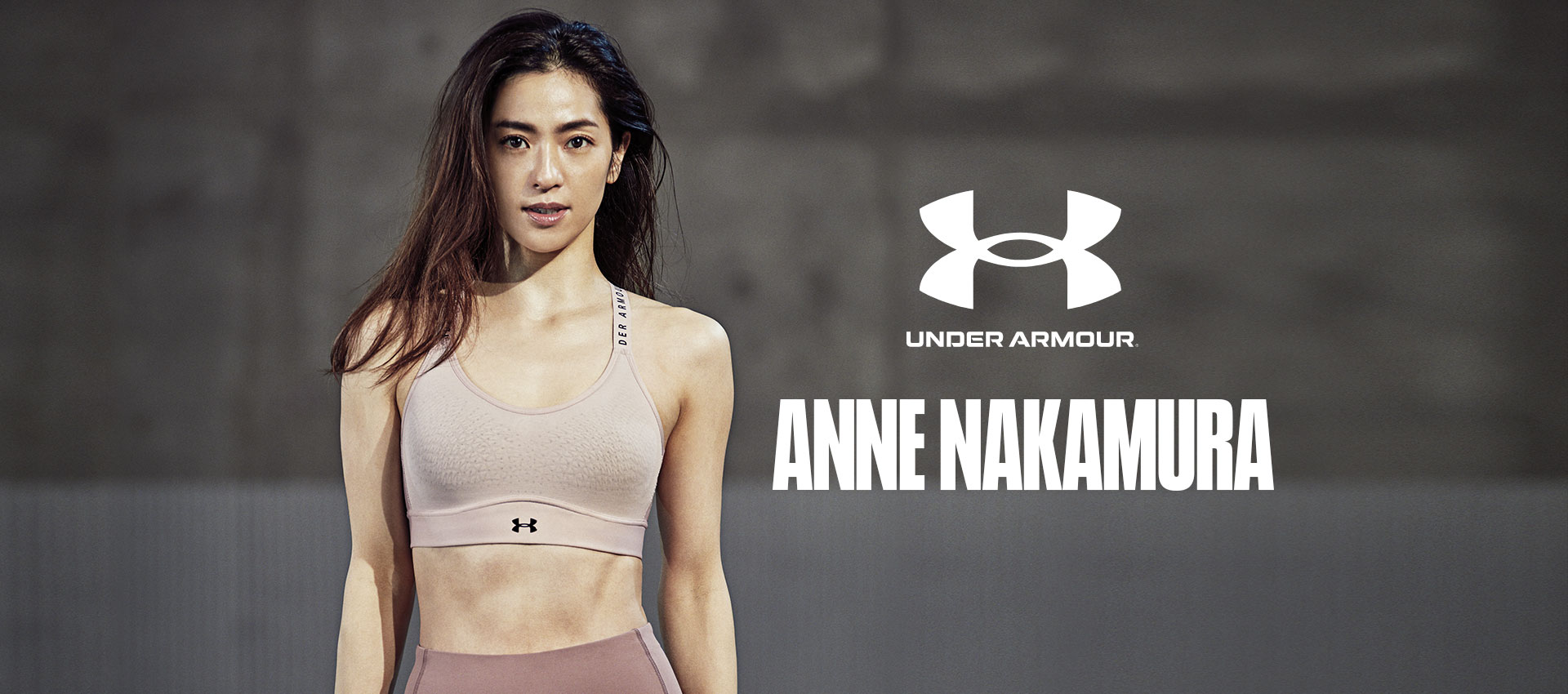逆手懸垂(チンアップ)の効果と正しいやり方|回数・頻度・順手との違い
懸垂運動(チンニング)には、順手で行う「順手懸垂(プルアップ)」を基本として、逆手で行う「逆手懸垂(チンアップ)」もあります。逆手懸垂は、手のひらを自分に向けてバーを握り、腕と背中を使って体を引き上げるトレーニングです。
順手よりも取り組みやすく、上腕二頭筋を効率的に鍛えられるため、初心者にも人気があります。背中や腕を引き締めるだけでなく、姿勢の改善や基礎代謝の向上にも効果的です。
<このページの内容>
逆手懸垂(チンアップ)と順手懸垂(プルアップ)のの違い
逆手懸垂の基本的な特徴や、順手との違いを整理します。どちらが良いというものではなく、狙う部位や目的に応じて使い分けることが大切です。
逆手懸垂(チンアップ)の特徴

逆手懸垂(チンアップ)は、手のひらを自分に向けてバーを握り、腕と背中を使って体を引き上げる方法です。順手に比べて上腕二頭筋の関与が大きいため、腕の力を意識しやすいのが特徴です。
また、肘を体の前に引きつける動作になるため、広背筋の下部にも刺激が入りやすくなります。初心者でも動作の感覚をつかみやすく、取り組みやすい握り方です。
順手懸垂(プルアップ)との違い

順手懸垂(プルアップ)は、手のひらを前に向けて握る方法で、広背筋全体を中心に負荷がかかります。背中の広がりを作りたい人には順手が適しています。
一方で逆手懸垂は、上腕二頭筋や広背筋下部への刺激が強く、力こぶや背中の厚みを出したい人に効果的です。どちらかが優れているわけではなく、目的に応じて選ぶことが大切です。
逆手しかできない人へのアドバイス
懸垂を始めたばかりの人は、順手よりも逆手のほうが楽に感じることが多いです。これは日常生活で腕を曲げる動作を使う機会が多く、上腕二頭筋に力を入れる感覚をつかみやすいためです。
逆手しかできなくても問題はありません。順手に挑戦したい場合は、ネガティブ動作やアシストバンドを取り入れて段階的に慣れていくと良いでしょう。
逆手懸垂(チンアップ)で鍛えられる筋肉と効果
逆手懸垂は腕と背中を中心に、複数の筋肉を同時に刺激できる効率的なトレーニングです。見た目の変化だけでなく、姿勢改善や代謝アップなど日常生活にも良い影響をもたらします。
広背筋下部と上腕二頭筋を効率的に刺激

逆手懸垂は、広背筋の下部と上腕二頭筋を強く使うのが特徴です。体を引き上げる際に肘を体の前に引く動作になるため、力こぶを作る筋肉である上腕二頭筋に負荷が集中します。

広背筋も全体的に刺激されますが、とくに下部に効かせやすく、背中の厚みを出すのに適しています。逆三角形のシルエットを目指す人にも効果的です。
前腕や体幹の補助的な効果
バーを握ることで前腕の筋肉にも強い刺激が加わります。握力の向上や腕全体の安定性を高める効果が期待できます。
また、動作中は体をまっすぐに保つ必要があるため、腹直筋や脊柱起立筋など体幹の筋肉も働きます。背中や腕だけでなく、姿勢を支える筋肉にも同時にアプローチできます。
姿勢改善・肩こり予防・代謝アップ
背中の筋肉を強化すると肩甲骨まわりの可動性が高まり、猫背の改善や肩こりの予防につながります。ぶら下がる動作自体にも姿勢を整える効果があります。
さらに、大きな筋肉を同時に鍛えるため基礎代謝が上がり、痩せやすく太りにくい体づくりにも役立ちます。日常生活での疲れにくさや体の引き締め効果も期待できます。
逆手懸垂(チンアップ)の正しいやり方
逆手懸垂は腕と背中を同時に鍛えられる効率的な動作ですが、フォームを誤ると効果が半減し、肩や肘を痛める原因にもなります。正しいやり方を理解し、初心者は段階的に練習を進めましょう。
基本フォームと手幅の目安
逆手懸垂は、肩幅と同じかやや狭めにバーを握るのが基本です。手のひらを顔側に向けて握り、腕をまっすぐ伸ばした状態でぶら下がります。
背筋を伸ばし、体をまっすぐ保つように意識してください。脚は組まずにそろえると、体幹の安定性も高まります。
動作手順(上げる→キープ→下ろす)
1.バーを肩幅程度の逆手で握る

2.息を吐きながら胸をバーに近づけるように体を引き上げる
3.顎がバーに届いたら1秒程度キープする
4.息を吸いながら体をゆっくり下ろす
反動を使わず、丁寧に繰り返すことが大切です。肘を完全に伸ばすことで可動域を最大限に使えます。
初心者向けアレンジ(斜め懸垂・ネガティブ・アシストバンド)
懸垂が難しい人は、まず斜め懸垂から始めましょう。足を地面につけて体を斜めにし、腕を引きつける動作を繰り返す方法です。
次のステップはネガティブ動作です。ジャンプして顎をバーの上まで持ち上げ、ゆっくり体を下ろします。強い筋力がつき、懸垂に近い動作が可能になります。
さらに、アシストバンドを使えば自体重の一部をサポートできるため、正しいフォームでの練習がしやすくなります。バンドを使ったやり方は下記記事で紹介しています。
やってはいけないNGフォーム
逆手懸垂では反動を使って体を引き上げるのは避けましょう。鍛えたい部位に負荷がかからず、怪我のリスクが高まります。
また、バーを強く握り込みすぎると腕だけで引き上げてしまい、背中への刺激が弱まります。背中と腕の両方を意識することが重要です。
背中を丸めて動作すると腰や肩に負担がかかるため、頭からかかとまでを一直線に保つよう意識してください。
逆手懸垂(チンアップ)の回数・頻度の目安
逆手懸垂は強度の高い自重トレーニングですが、初心者でも段階的に取り組めば無理なく続けられます。回数の目安と、理想的な頻度について解説します。
初心者は1回でも効果あり
懸垂は1回できるだけでも十分に負荷がかかります。とくに逆手は上腕二頭筋を使いやすいため、初心者でも1回から挑戦しやすい方法です。
無理に回数を増やす必要はなく、まずは正しいフォームでできる回数を継続することが大切です。
目標は10回×3セット
慣れてきたら10回を1セットとし、3セットを目安に取り組むとよいでしょう。インターバルは30秒から1分程度を挟むと、筋力と持久力の両方を伸ばせます。
ただし、回数を重視するよりも可動域を広く使った動作を意識することで、効率的に筋肉を刺激できます。
毎日やっていい?週2〜3回が理想
筋肉には回復期間が必要です。懸垂は自重トレーニングですが、とくに広背筋や上腕二頭筋など大きな筋肉を使うため、毎日続けると回復が追いつかない場合があります。
筋肉痛が強く残っているときは休養を優先し、週2〜3回を目安に取り組むと効果的です。中級者以上で疲労が少ない場合は、2日に1回のペースでも問題ありません。
逆手懸垂(チンアップ)の効果をさらに高める方法
逆手懸垂は効率的に背中と腕を鍛えられますが、生活習慣や補助的な工夫を取り入れることで効果をさらに引き上げられます。ここでは実践しやすいポイントを紹介します。
食事とPFCバランスを意識する
筋肉を成長させるには、消費カロリー以上の摂取が必要です。とくにタンパク質だけでなく、エネルギー源となる糖質を適切に摂ることが重要です。
食事のバランスは「P=タンパク質」「F=脂質」「C=炭水化物」を意識し、偏りのない栄養管理を心がけましょう。過不足なく摂ることで筋肉の成長を支えられます。
運動前後のタンパク質補給
近年の研究では「トレーニング後30分以内」に限定する必要はないとされています。大切なのは、運動の前後を含めた数時間のうちに十分なタンパク質を摂取することです。
鶏胸肉や魚、大豆製品など食事から摂るのはもちろん、タイミングが難しい場合はプロテインを利用すると効率的です。1日を通して必要量を満たせているかを優先しましょう。
睡眠と休養をしっかり取る
筋肉はトレーニング中ではなく、休んでいるときに成長します。とくに睡眠中に分泌される成長ホルモンは、筋肉の修復と発達に欠かせません。
7〜8時間の睡眠を目安に、就寝前はスマホやカフェインを避けて質の高い睡眠を心がけましょう。疲労が残っているときは休養日を設け、超回復を促すことが効率的です。
逆手懸垂(チンアップ)に関するQ&A
Q1:効果はどれくらいで出ますか?
個人差はありますが、正しいフォームで週2〜3回続けると、2〜3か月程度で背中や腕の変化を感じる人が多いです。姿勢の改善など機能的な効果は、さらに早く体感できる場合もあります。
Q2:女性でも逆手懸垂をして大丈夫ですか?
もちろん可能です。逆手懸垂は自重を使った運動なので、過度に筋肉が大きくなる心配はありません。背中や二の腕を引き締めたい女性にもおすすめです。アシストバンドやネガティブ動作から始めると無理なく継続できます。
Q3:順手と逆手、どちらを優先すべきですか?
目的によって使い分けましょう。背中の広がりを重視するなら順手、力こぶや背中下部を強調したいなら逆手がおすすめです。両方を取り入れることで、上半身をバランスよく鍛えられます。
監修者プロフィール
なか整形外科京都西院リハビリテーションクリニック
院長 樋口 直彦 先生
 帝京大学医学部卒業後、いくつかの病院で勤務し、院長を経験後、2021年1月に医療法人藍整会 なか整形外科の理事長に就任。バレーボールVリーグ「サントリーサンバーズ」のチームドクターも務める。骨折治療をはじめ関節外科、スポーツ整形外科を専門に治療。
帝京大学医学部卒業後、いくつかの病院で勤務し、院長を経験後、2021年1月に医療法人藍整会 なか整形外科の理事長に就任。バレーボールVリーグ「サントリーサンバーズ」のチームドクターも務める。骨折治療をはじめ関節外科、スポーツ整形外科を専門に治療。
<Photo:角谷剛>
<Edit:編集部>

 懸垂(チンニング)バーの握り方|順手、逆手、広く握る、狭く握る…効果の違いは?
懸垂(チンニング)バーの握り方|順手、逆手、広く握る、狭く握る…効果の違いは? 懸垂を毎日続けるとどうなる?「1日5回」でも体は変わる![トレーナー解説]
懸垂を毎日続けるとどうなる?「1日5回」でも体は変わる![トレーナー解説]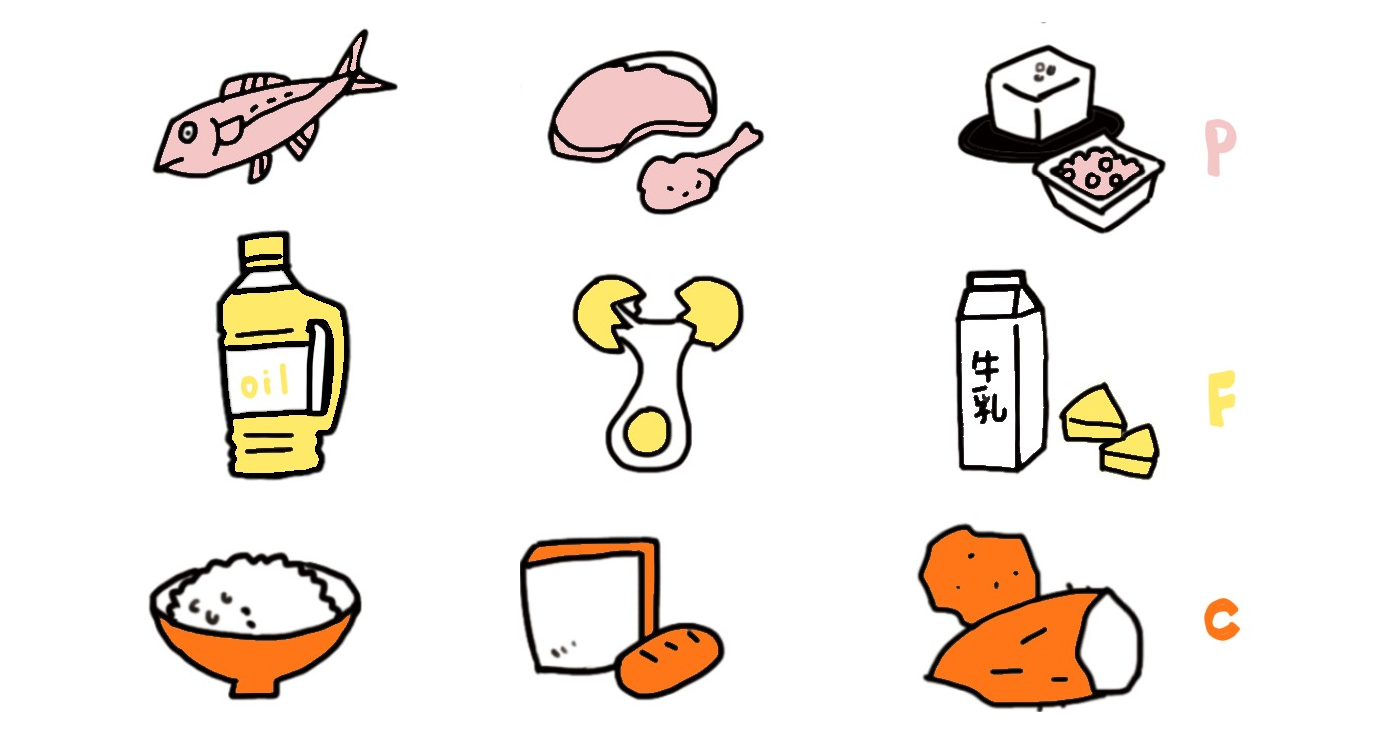 PFCバランスとは。計算方法を解説!たんぱく質・脂質・炭水化物の理想量を知りたい人へ
PFCバランスとは。計算方法を解説!たんぱく質・脂質・炭水化物の理想量を知りたい人へ 懸垂(チンニング)のすごい効果とは。5回、10回…毎日やると体にどんな変化が出てくる?
懸垂(チンニング)のすごい効果とは。5回、10回…毎日やると体にどんな変化が出てくる?