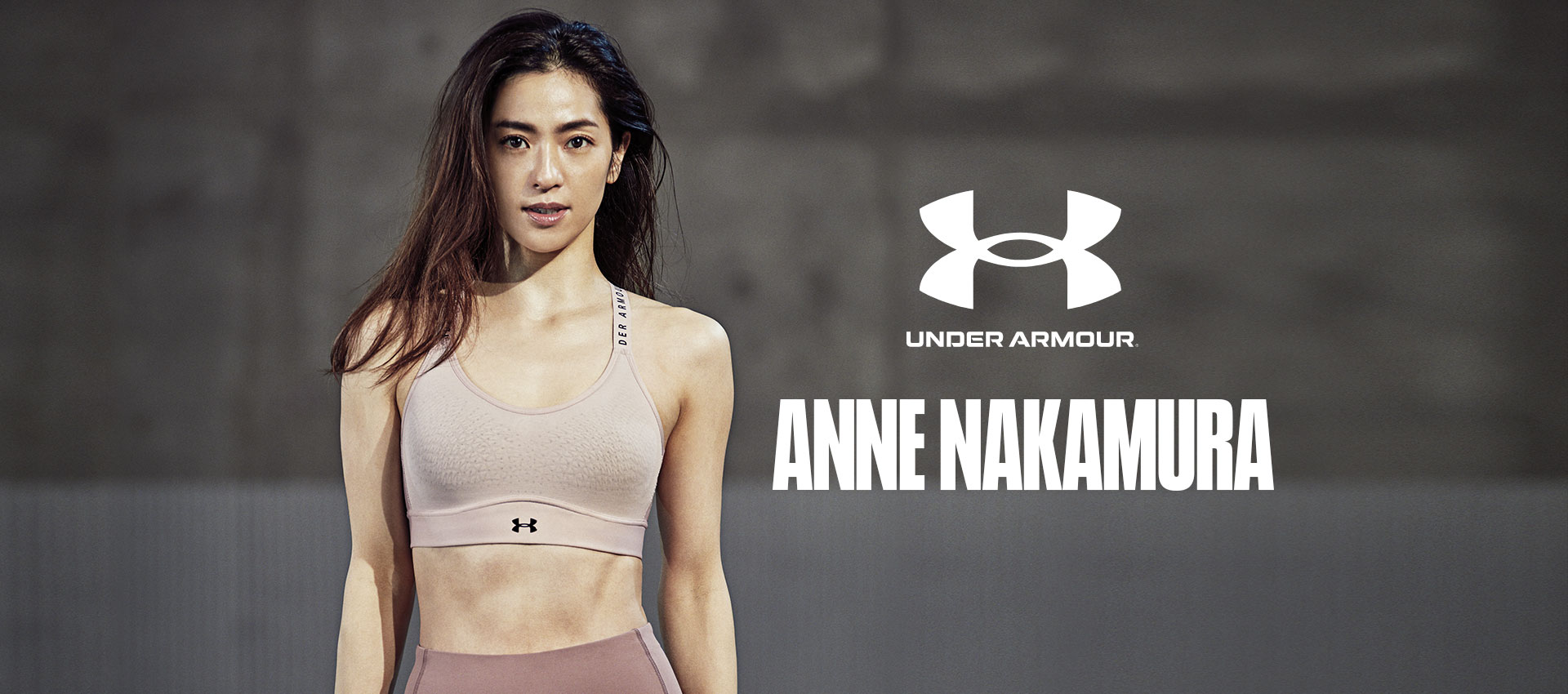筋トレは毎日やるべき?週に何回が効果的?トレーニングの頻度と回数 (2/2)
筋トレの負荷と回数の決め方
重量と回数は一律決まっているものではなく、個人の筋力や目的によって異なります。
「筋力を向上させたい」「筋肉を大きく(バルクアップ)したい」「細マッチョになりたい」「ダイエットでカラダを引き締めたい」など、それぞれの目的に合わせて強度を決める必要があります。
筋力向上が目的の場合
「重いものを持ち上げられる体力をつけたい」「競技スポーツのパフォーマンスアップのために筋力を向上させたい」といった“筋力向上”が目的の場合は、3〜7回程度で限界を迎える負荷設定を行う必要があります。
筋肥大が目的の場合
「バルクアップして細マッチョになりたい」「カラダを大きくしたい」というような“筋肥大”を目的とする場合は、8〜12回程度で限界を迎える負荷設定で行いましょう。
ダイエットのために筋肉を増やして脂肪燃焼を促したい場合も、この重量設定で行うのがオススメです。
筋持久力が目的の場合
「同じ動作を繰り返し長時間行えるようにしたい」「疲れにくくしたい」といった “筋持久力”を目的とする場合は、13~20回程度で限界を迎える負荷設定が効果的です。
よくある回数を増やしていく筋トレのやり方は、この筋持久力を高める方法になってしまい、筋力や筋肥大効果は大きくありません。
逆に筋持久力を高めたい人は、回数をどんどん増やしていく方法でもよいでしょう。
筋トレの重量と回数は「過負荷の原則」に従って考える
強度設定を考えるとき、男性・女性問わず覚えておいてほしいのが、トレーニング5原則における「過負荷の原則」です。これは、ずっと同じ刺激量ではカラダは成長せず、より多くの負荷を与えることによって成長していくという理論です。
たとえば、5回で限界になる10kgの重量を使っていたとしましょう。しかし同じ10kgの重量を使い続けていても、慣れてくると筋トレ効果は現れなくなってきます。
とくに初心者の場合、使用していた重量が軽く感じられるようになっても、加重せず回数を多くする人が多いようです。
負荷は高まりますが、効率的ではありません。
太い腕になりたい、たくましく引き締めたい場合、回数を増やすのではなく、ダンベル追加やトレーニングバンドをつける、フォームを変えるなど回数以外で負荷を高める必要があります。

カラダを成長させるためには、たとえ自重トレーニングであっても負荷を増やし続ける必要があるのです。
重量以外に負荷強度を高めるには
ちなみに重量以外に負荷強度を高める方法は以下です。
セット間の休憩時間を短くする
セット間の休憩を短くしてみましょう。普段2分以上休んでいるのであれば休み過ぎです。10~30秒くらいで設定してみてください。
セット間の休憩時間を短くすることで、1回のトレーニング時間を短くすることが可能です。また、休憩中の心拍数の低下を防ぐことができ、ダイエットにも効果を発揮します。
可動域をできるだけ大きくする
可動域(関節が動く範囲)をできるだけ大きくすることによって、筋肉全体に負荷がかかり、力を発揮している時間も長くなるため、筋トレの負荷が高まります。
可動域が狭くなってしまう原因として多いのは、重すぎる重量を使っている、もしくは可動域を大きく動かすメリットを理解していない場合です。
可動域を大きく使うために、筋トレ前にはウォームアップを行うようにしましょう。
動作スピードをゆっくり行う
動作のスピードを意識的にゆっくりすることでも、筋肉への刺激を大きくすることができます。
とくに筋肉が引き伸ばされながら力を発揮するエキセントリック局面で、ゆっくり行うように意識するとよいでしょう。
具体的には、スクワットの腰を下ろす動作やバーベル・ダンベルを下ろす動作時は、ゆっくり行うと負荷が高まります。
動画でまとめておさらい!

「面倒だな…」という人はパーソナルジムに丸投げ!
ダイエット成功の鍵は「運動2:食事8」!トレーニングの頑張りを無駄にしないお弁当
AD
詳細を見る
著者プロフィール
和田拓巳(わだ・たくみ)
プロスポーツトレーナー歴16年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院での治療サポートの経験もあり、ケガの知識も豊富でリハビリ指導も行っている。スポーツ系専門学校での講師や健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師経験も多数。そのほか、テレビや雑誌でも出演・トレーニング監修を行う。日本トレーニング指導者協会JATI-ATI。
公式サイト/公式Facebook
<Text:和田拓巳/Photo:Image by AI素材.com>

 筋トレの重量設定と回数、よくある「間違った決め方」とは
筋トレの重量設定と回数、よくある「間違った決め方」とは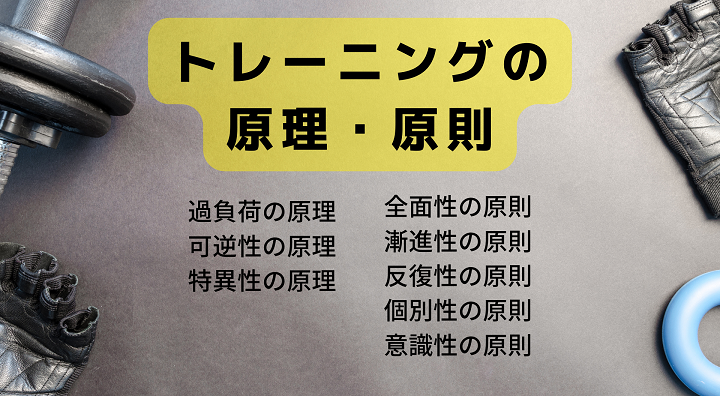


 【2024】ライザップの無料カウンセリング行ってきた!値段や口コミ、リバウンドするか気になる~
【2024】ライザップの無料カウンセリング行ってきた!値段や口コミ、リバウンドするか気になる~