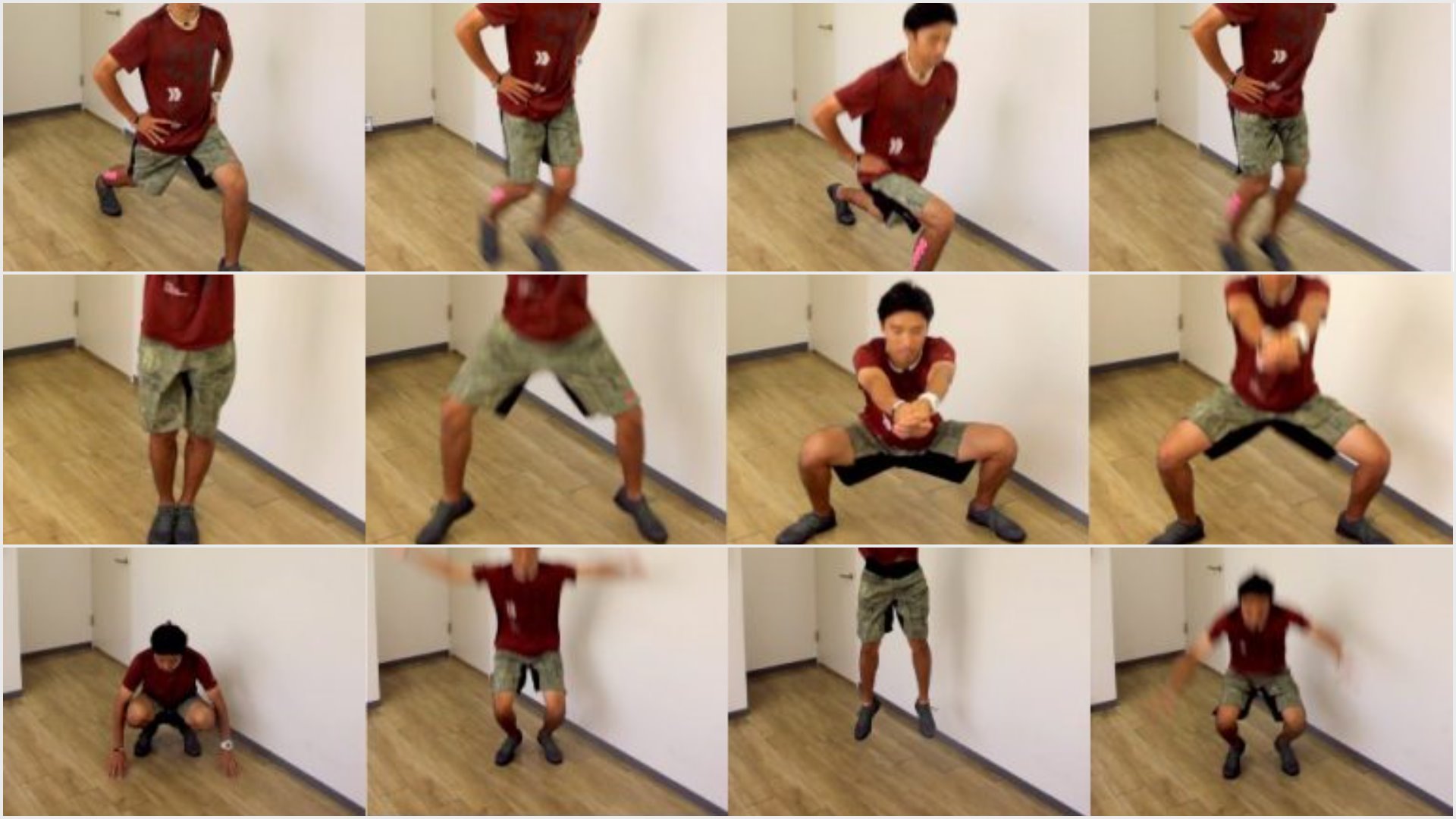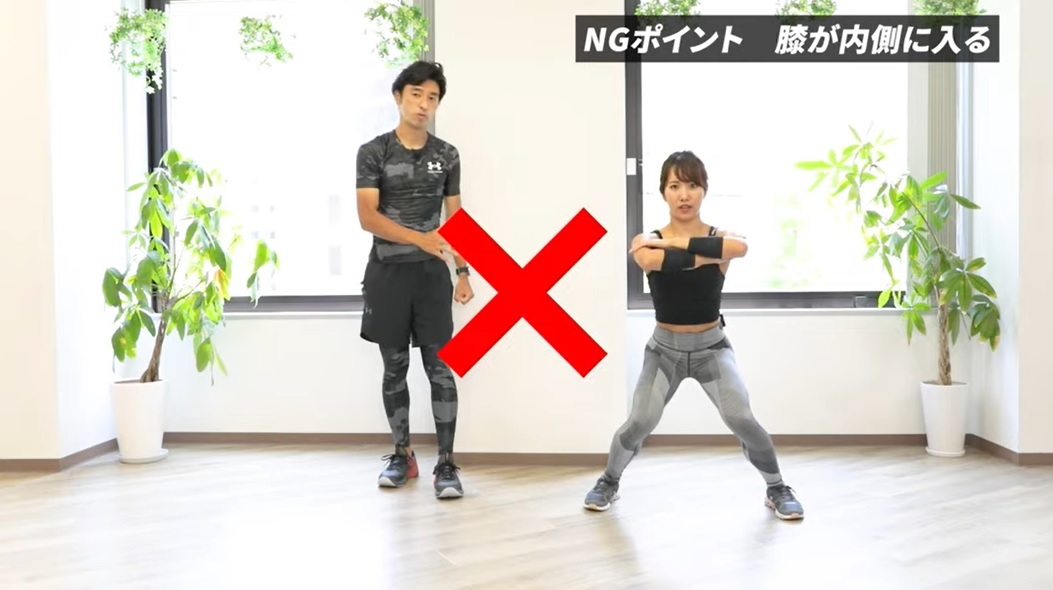フィットネス
2025年4月15日
筋トレの王道「スクワット」の効果とやり方|正しい姿勢、フォームの種類、回数 (1/3)
自重筋トレ「スクワット」。簡単に見えますが、実は奥深いメニュー。
正しい仕方で行わないと、腰痛や膝の痛みの原因になるほか、意図しない場所を鍛えてしまいがち。
今回は、スクワットの種類と効果、正しい姿勢フォーム、回数のほか、負荷設定など解説していきます。
スクワットの効果とは
大きな筋肉が鍛えられ、効率よく筋力アップできる
スクワットはおもに、下半身を鍛えるフリーウエイトトレーニングです。 “筋肉BIG4”と呼ばれる大きな筋肉(胸・背中・腹筋・太もも)が鍛えられるため、効率よく筋力アップを狙うことができます。
筋力が増えると基礎代謝も上がるため、食べても太りにくくなる、日常の消費カロリーが増えるなど、ダイエットにもうれしい効果が期待できます。
下半身の柔軟性を高める
下半身の柔軟性と安定性、足の筋力も身につくため、ランニングをする人にもおすすめです。
ケガ予防として、運動前の動的ストレッチに取り入れるアスリートも少なくありません。
スクワットはどこに効く? 鍛えられる筋肉部位
スクワットでは、おもに以下を鍛えることができます。
- お尻(大臀筋)
- 太ももの前側(大腿四頭筋)
- 太ももの裏(ハムストリングス)
- ふくらはぎ(ひふく筋・ヒラメ筋)
- 背中(脊柱起立筋)
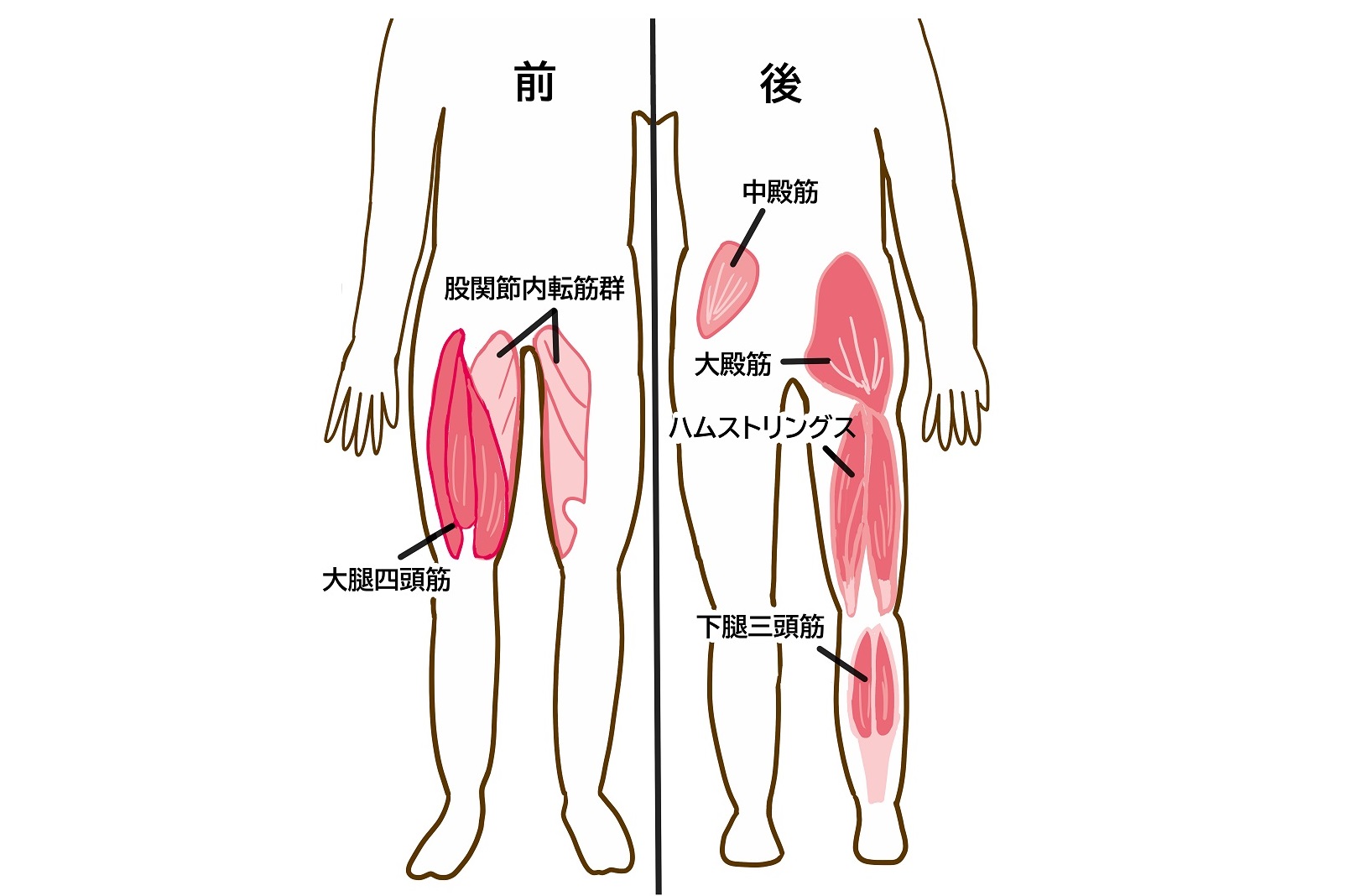
スクワットの正しいフォームとやり方
まずは、一般的なスクワット「ノーマルスクワット」から解説します。
ノーマルスクワットのやり方
- 足を腰幅に開き、つま先は膝と同じ向きにする
- お尻を後ろへ突き出すように、股関節から折り曲げる
- 太ももが床と平行になるまで下ろしたら、ゆっくりと元の姿勢に戻る


肩甲骨を寄せて下げ、自然な背筋を保ちます。膝がつま先よりも前に出ないよう注意!

 マラソンランナーも「筋トレ」をやるべき理由とは。高重量×低回数トレーニングで効果的に筋肉をつける
マラソンランナーも「筋トレ」をやるべき理由とは。高重量×低回数トレーニングで効果的に筋肉をつける 
 スクワットをすると腰が痛い!なぜ腰にくる?原因と対処法[重症膝痛専門整体師監修]
スクワットをすると腰が痛い!なぜ腰にくる?原因と対処法[重症膝痛専門整体師監修]