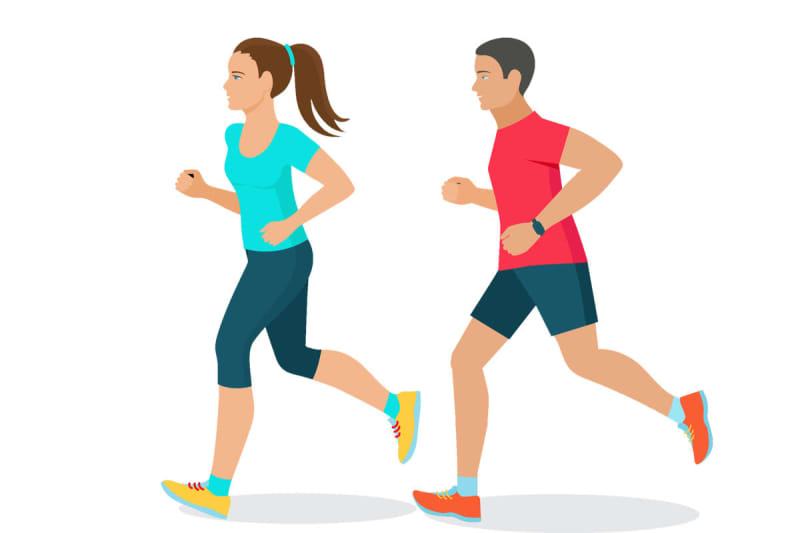1日ひと掴みの「くるみ」で、 思春期の「注意欠陥多動性障害(ADHD)」が改善される可能性 (1/2)
カリフォルニア くるみ協会から嬉しいニュースが。
くるみを1日ひとつかみ食べることで、思春期の「注意欠陥多動性障害(ADHD)」症状によい影響を与える可能性があるというのです。
くるみが持つ「オメガ3脂肪酸」は、脳の発達と機能に重要な栄養素
世界でもっとも評価が高い医学雑誌のひとつ「ランセット」が発行する『eClinicalMedicine』発表の研究※1によると、以下が報告されました。
1日ひとつかみのくるみ(30g)を含む食生活を送った中高生の、注意欠陥多動性障害(ADHD)を含む注意機能の改善や流動性知能※2関連の機能向上、神経心理学的機能※3の改善
くるみはナッツの中で唯一、発育段階における脳の発達に重要な役割を果たし、オメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)を豊富に含んでいます。

脳の発達には大量のエネルギーと栄養素を必要とするため、必須栄養素が不足すると、最適な成熟が妨げられる可能性があります。
オメガ3系脂肪酸は、脳の発達と機能に重要な栄養素と考えられています。
認知機能とナッツとの関係は昔から注目されている
今回の最新研究結果について、長年、認知症の研究に携わっている朝田隆先生(メモリークリニックお茶の水院長、筑波大学名誉教授)は、以下のように評価しています。
昔から小学校のクラスに1人か2人はいる落ち着きのない子の多くが、近年、注意欠陥多動性障害(ADHD)だと知られるようになりました。
従来は子供の病気で大人になれば半分の人は治るとされていましたが、必ずしもそうでなく、最近では、職場での不適応等により大人になったADHDが注目されています。
この研究は、注意欠陥多動性障害(ADHD)者の注意や流動性知能などの認知機能に対してくるみが有効だと報告しています。
実は認知機能とくるみを始めとするナッツとの関係は、がんや心臓病と同様に以前から注目され、認知症予防の食事なら地中海食が定番であるとされていました。その特徴の1つが抗酸化作用をもつオメガ3系脂肪酸のくるみを食べることです。
ADHDは注意や段取りの司令部である前頭前野の障害とされています。本研究のポイントは発達段階の思春期なら、くるみが脳の障害を改善するとした点です。つまりくるみには成長によるADHDの改善を後押しする力があると考えられます(朝田 隆先生)
朝田 隆先生
認知症の早期発見・早期治療に特化した「メモリークリニックお茶の水」理事長・院長。東京医科歯科大学客員教授。筑波大学名誉教授。認知症予防と治療の第一人者。40年にわたり、1万人を超える認知症、および、その予備群である軽度認知障害の治療に従事するとともに、テレビや新聞、雑誌での啓発活動を続けている。著書多数
次:研究の詳細

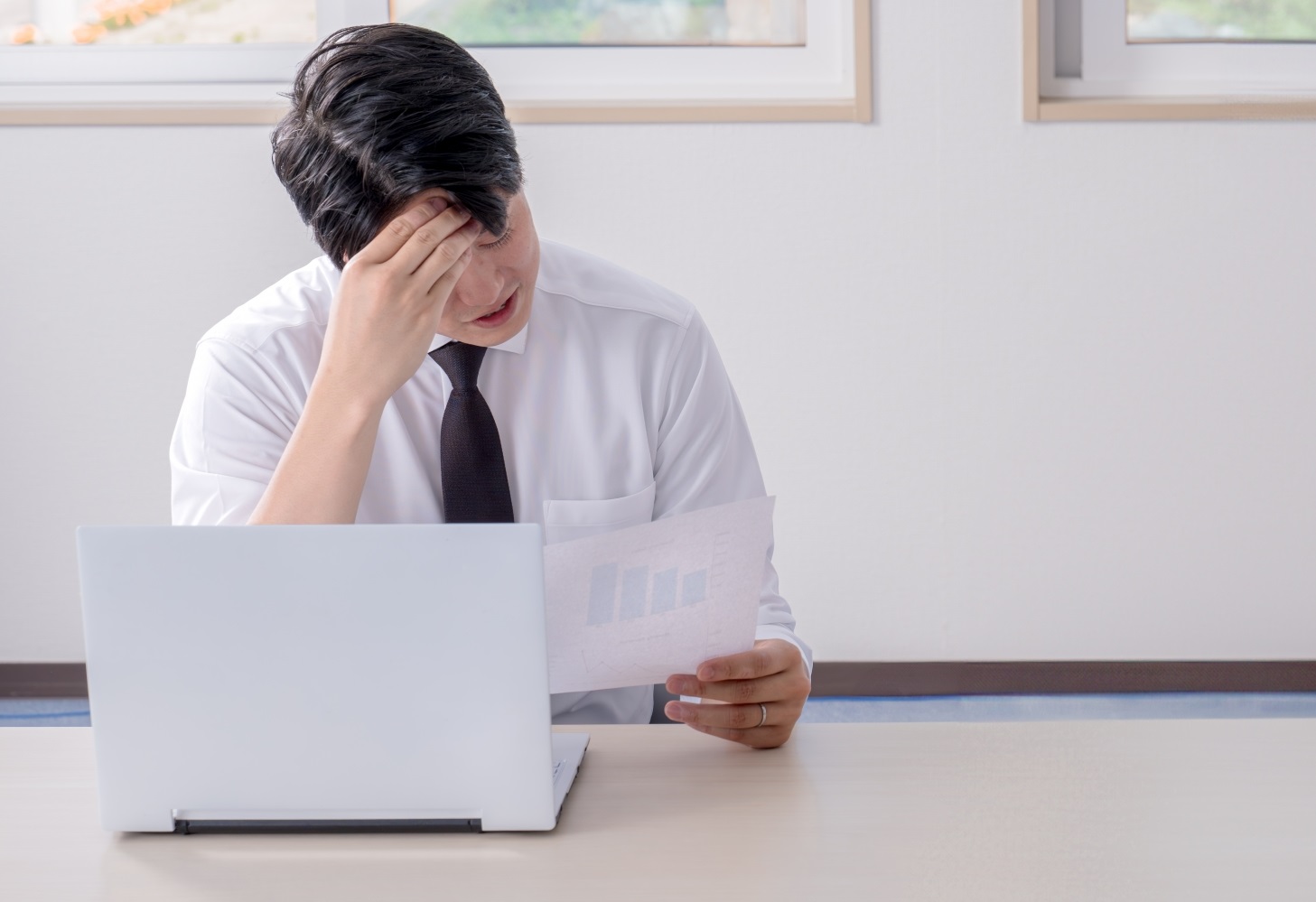 発達障害(ADHD)の人と会話が噛み合わないのはなぜ?その理由と対処法
発達障害(ADHD)の人と会話が噛み合わないのはなぜ?その理由と対処法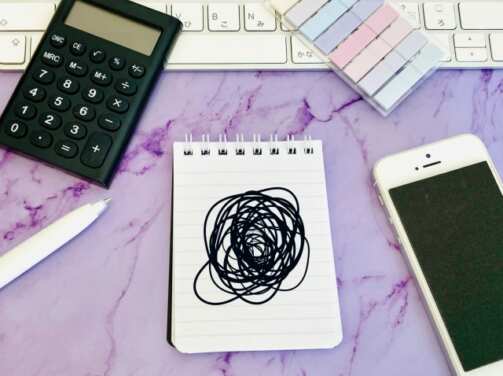 なぜADHDだと「頭がごちゃごちゃ」するのか?その理由と整理方法
なぜADHDだと「頭がごちゃごちゃ」するのか?その理由と整理方法
 ナッツの食べ過ぎ、なぜ危険?デメリットと摂取量の目安、注意点[薬剤師監修]
ナッツの食べ過ぎ、なぜ危険?デメリットと摂取量の目安、注意点[薬剤師監修]