
フィットネス
2024年5月10日
なぜ?腕立て伏せ(プッシュアップ)ができない原因と練習方法 (1/3)
腕や胸など、上半身を鍛える自重トレーニング「腕立て伏せ(プッシュアップ)」。筋トレメニューに加えている人も多いなか、「実は腕立て伏せができない」という人も少なくないはず。
腕立て伏せは、簡単なようで意外とキツい種目です。とくに女性や体力がない男性にとっては、思うようにカラダが持ち上がらないと感じることが多いでしょう。しかし筋力が向上すれば、誰でも必ずできるようになります。
腕立て伏せができない理由
腕立て伏せができない理由は二つ。まず挙げられるのが主働筋(ある動作において主となる役割を果たす筋肉)である「大胸筋」の筋力不足です。
原因1 大胸筋の筋力不足
腕立て伏せの動作でもっとも力を発揮するのが大胸筋。大胸筋は胸の大きな筋肉で、腕立て伏せでカラダを一番下に下ろし、上げていくときに力を発揮します。
また、一番下にカラダを下ろした状態は、大胸筋の筋力がもっとも出しにくい関節角度(スティッキングポイント)となります。
深く腕立て伏せができないという人は、大胸筋の筋力不足が考えられるでしょう。
原因2 上腕三頭筋の筋力不足
もう一つの理由が、「上腕三頭筋」の筋力不足。上腕三頭筋は腕の後ろ側の筋肉で、肘を伸ばすときに力を発揮する筋肉です。
腕立て伏せの場合、上腕三頭筋は大胸筋のサポートをして力を発揮する筋肉で、カラダを途中から一番上まで持ち上げるときに力を多く発揮します。
胸よりも腕が先に疲れてしまう人は、上腕三頭筋の筋力不足が考えられるでしょう。
筋トレ初心者は「膝をついた腕立て伏せ」から練習
まずは膝をついた「膝つき腕立て伏せ」からスタートします。
膝つき腕立て伏せのやり方
- 両手を肩幅よりも少し大きめに床につき、膝をつけて足は浮かせる
- 背中に力を入れて肘を曲げ、体を限界まで下げていく
- 少しキープしたら、手のひら全体で身体を押し上げる
10回×3セットを目安に行いましょう。

 背中は丸めたり反ったりせずまっすぐをキープします。
背中は丸めたり反ったりせずまっすぐをキープします。
 しかし、この「膝をついた腕立て伏せ」すら難しいという人も珍しくありません。その場合、どんなトレーニングメニューから始めるのが有効でしょうか。
しかし、この「膝をついた腕立て伏せ」すら難しいという人も珍しくありません。その場合、どんなトレーニングメニューから始めるのが有効でしょうか。




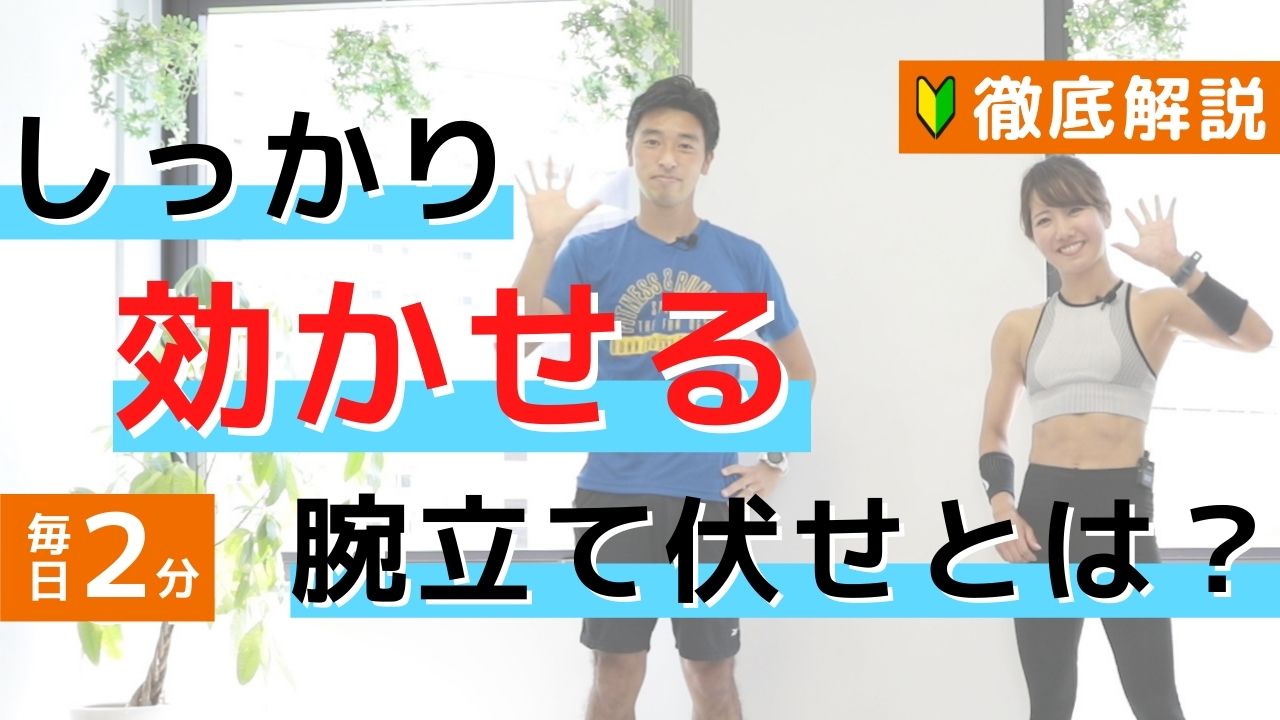








![ヨーグルトはダイエットにいい?ダメ?太らない食べ方と選び方、市販のおすすめ3選[管理栄養士]](https://contents.melos.media/wp-content/uploads/2023/10/12162634/23585134_s-240x160.jpg)





