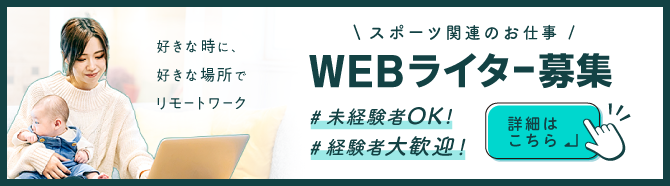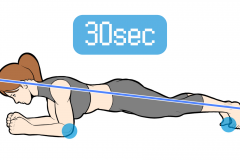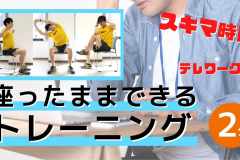【7/10は納豆の日】スゴイ効果・起源・食べない方が良い基準など…「雑学&豆知識」をまとめてみた (1/2)
本日、7月10日は納豆の日! お安くて栄養豊富な納豆は、食卓のレギュラーメンバーですよね。そんな納豆のことを、改めて知っていきましょう。納豆の雑学や豆知識などをまとめてみました。
納豆の起源
納豆の起源には、いくつかの「説」が存在します。どれが本当なのかは実のところ謎なのです……。
弥生時代説
納豆の原材料である大豆の栽培が普及した弥生時代、竪穴式住居の床に敷いた稲ワラに落ちた煮豆が自然発酵して納豆になったという「弥生時代説」。
聖徳太子説
聖徳太子の馬のエサの煮豆が余り、もったいないとワラに包んでおいたら自然発酵して糸を引く豆となっており、食べたらおいしかったので人々に広めたという「聖徳太子説」。
源義家説
平安時代、源義家が奥州遠征で農民に煮豆を差し出すよう命令した際、急ごしらえで煮豆をよく冷まさずに俵に詰めたため、数日後に納豆になっていたという「源義家説」。
加藤清正説
戦国大名・加藤清正が朝鮮出兵の際に煮豆を俵に入れて保存し、しばらくしたらいい匂いがするので開けてみたら納豆になっていたという「加藤清正説」。
納豆のスゴイ効果
ゆでた(蒸した)大豆に納豆菌を加えて発酵させた発酵食品である納豆。この納豆菌は、胃酸に負けることなく、生きたまま腸内にたどり着き、もともといる善玉菌を活性化します。そして悪玉菌を抑制し、腸内環境を改善させる働きが期待できます。
腸内環境を整えることで、
- 瘦せやすい体を作る
- 免疫機能を整える
- 便秘解消
このような効果が期待できます。
納豆にはどんな栄養素が含まれている?
納豆にはヒトの健康維持のために必要不可欠なたんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルといった5大栄養素がすべて含まれ、第6の栄養素といわれる食物繊維も豊富に含まれています。
大豆自体も栄養豊富な食品ですが、大豆が発酵して納豆になることで、とくにビタミンB2やビタミンKが多くなります。発酵過程の納豆菌により、大豆が本来持っている成分に加えて、新たに加わる成分にも注目です。
▼ この記事も読まれています
驚きの納豆パワー!その効果効能と、筋トレ民にうれしい栄養素とは